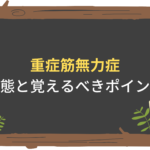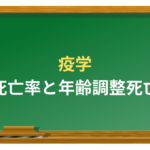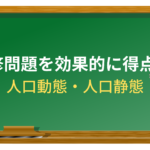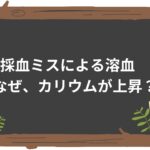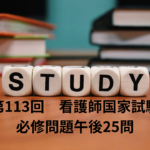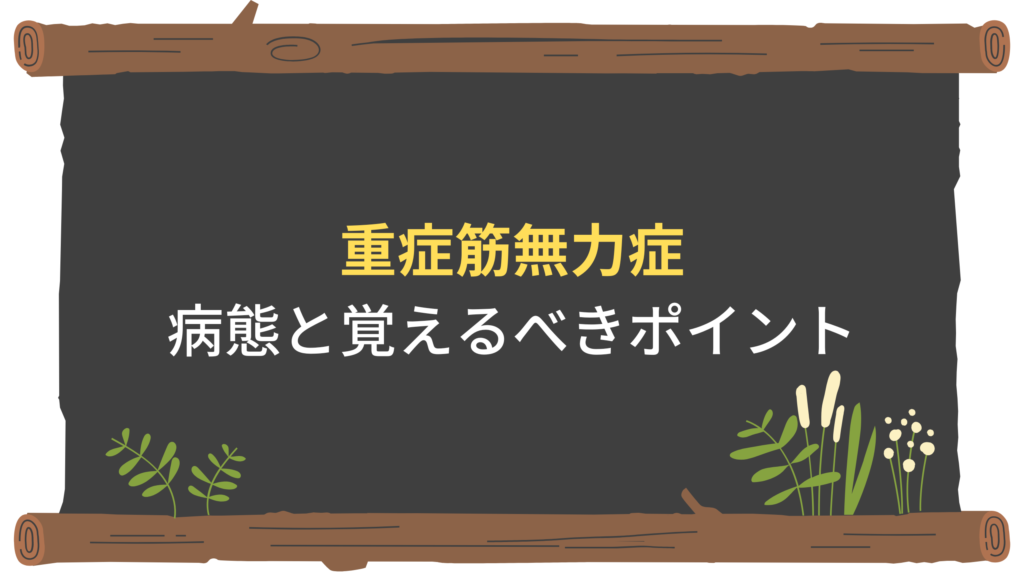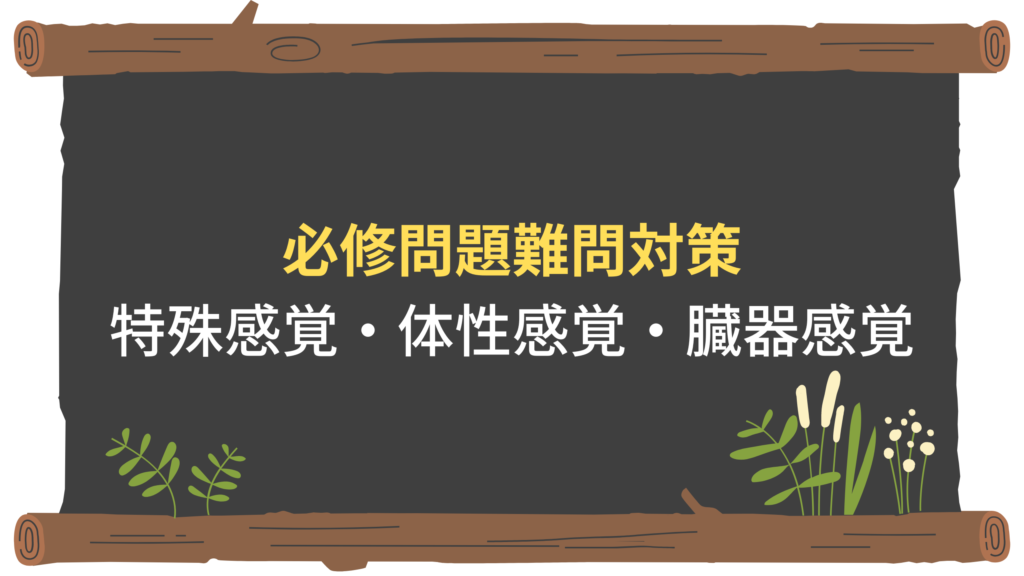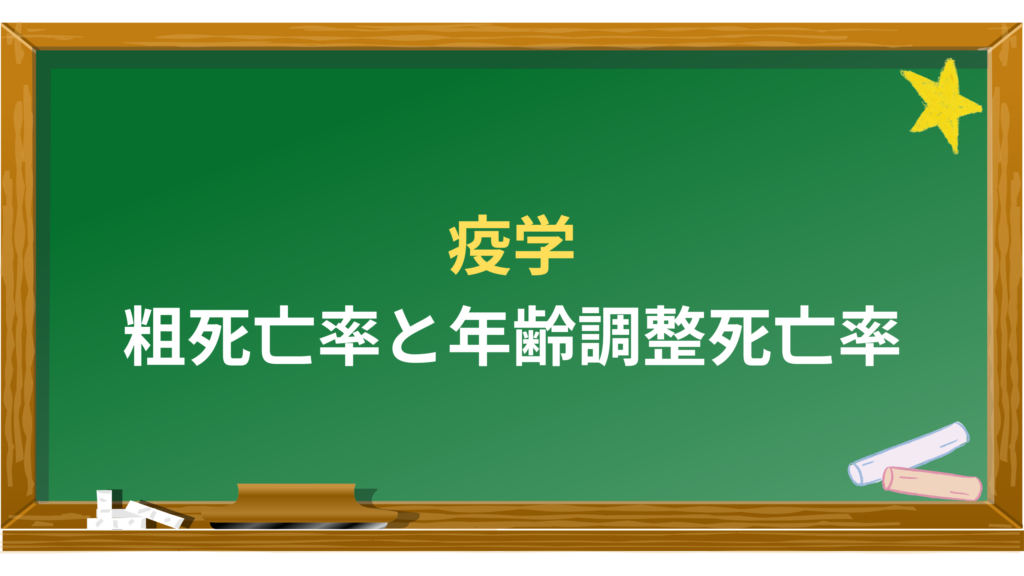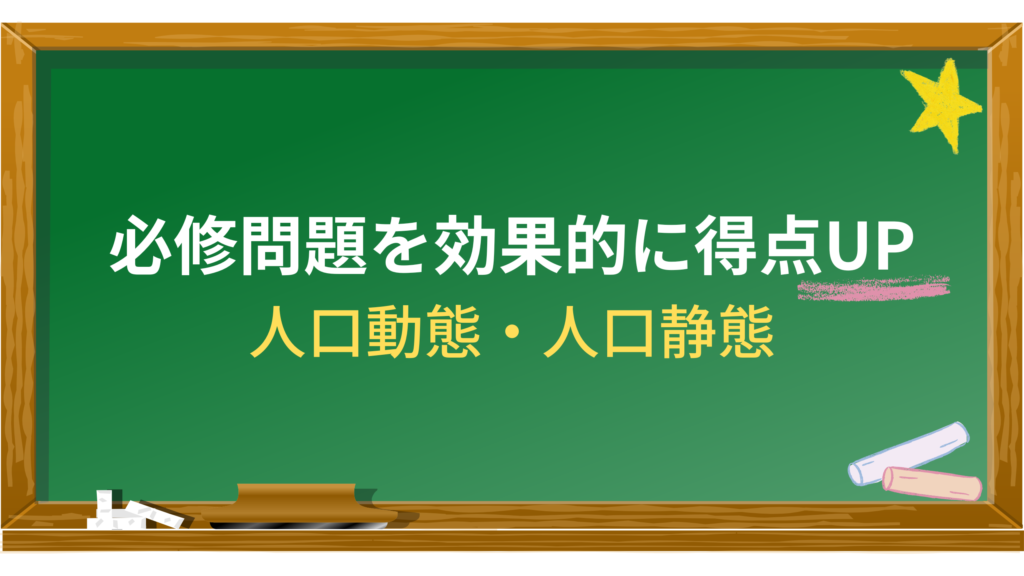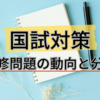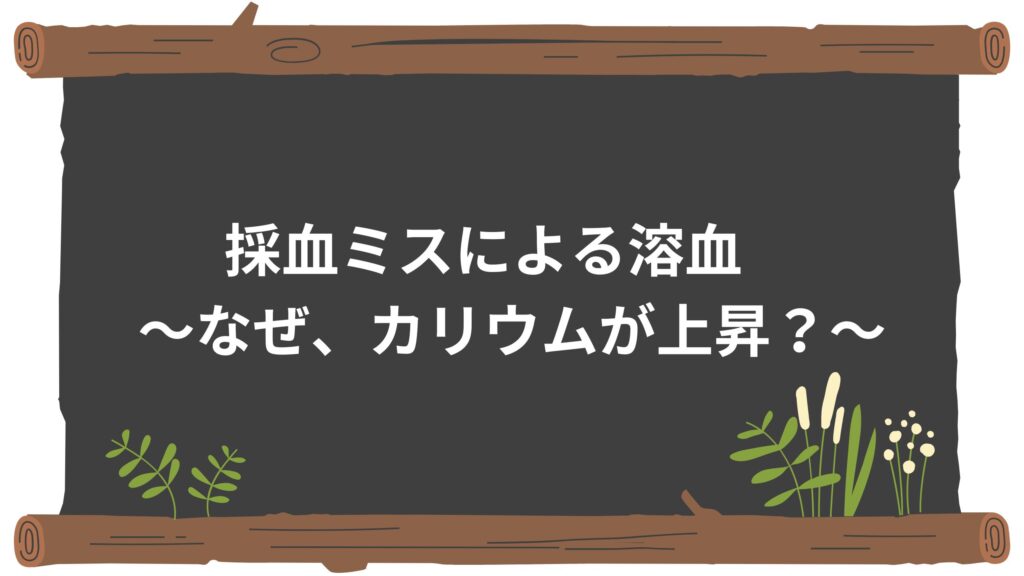こんにちは、講師のサキです。
今回は、重症筋無力症(MG)に関する記事です。
脳神経系は目に見えない、イメージしにくいということで敬遠されがちですが、ポイントを掴んで理解しておくことが重要です。
国家試験で問われるポイントを中心に解説していきます。
重症筋無力症とは
名称の通り、筋力が無力化してしまう病気です。
手足を動かすとすぐに疲れる、まぶたが下がってしまう(眼瞼下垂)などの状態になります。
筋力が弱ってしまう、力が入らなくなる原因は何なのかを理解することが重要です。
重症筋無力症の原因は?
筋肉が原因そうに思えますが、そうではありません。
筋肉を動かすために必要なアセチルコリンの伝導に原因があります。
(補足:骨格筋と副交感神経ではアセチルコリン、交感神経ではノルアドレナリン)
筋肉を動かすためには、脳からの司令であるアセチルコリンを筋肉が受け取ることが必要です。
しかし、重症筋無力症では、神経の接合部にアセチルコリンを受け取るのことを妨げる抗体(抗アセチルコリン受容体抗体)が体内で作られてしまい、脳からの司令を筋肉が受け取りにくくなっています
そのため、筋肉を動かしにくい、すぐに疲れるなどの症状が出現します。
(自己免疫疾患に分類されます)
重症筋無力症の治療:抗コリンエステラーゼ薬の内服
アセチルコリンが伝わりにくい状態であるため、アセチルコリンを増やすような治療になります。
コリンエステラーゼは神経末端から放出されるアセチルコリンを分解するので、コリンエステラーゼの働きを阻害することで、アセチルコリンを分解するのを防ぐことができます。
結果的に、筋肉まで届くアセチルコリンの量を増やすことができます。
重症筋無力症の合併症:胸腺腫
胸腺は、免疫に関係する器官ですが、重症筋無力症の患者さんは胸腺肥大を合併することが多々あります。
胸腺腫を合併した場合には、手術で胸腺を摘出することもあります。
重症筋無力症の症状
病態を理解すると症状もなんとなく想像しやすいかと思います。
筋肉が疲れやすい、力が入らない、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、複視などの症状が出ます。
症状は朝よりも夕方に強くなる傾向があります。
女性に多く、年齢層は小児から成人まで幅広くかかります。
重症筋無力症に類似した症状(名称や疾患)
筋肉が動かなくなる疾患として、以下のようなものがありますので、合わせて覚えていきましょう。
◉筋萎縮性側索硬化症(ALS)
上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの障害が同時にみられ、徐々に全身の筋肉が萎縮する進行性の疾患です。
◉脳梗塞
上位運動ニューロンの障害で、片麻痺を生じます。
◉ギランバレー症候群
急性の運動麻痺を起こす自己免疫性の末梢神経障害で、四肢の筋力低下がみられます。末梢神経の髄鞘に対する自己抗体(抗ガングリオシド抗体)が産生されて、運動神経、感覚神経が障害されます。
まとめ
重症筋無力症は、筋力低下や易疲労感がみられ、日内変動があったり、休息すると筋力が回復するといった特徴がある。
原因は、骨格筋の神経筋接合部において、アセチルコリン受容体が自己抗体により攻撃され、神経から筋への刺激伝達が障害されるためである。