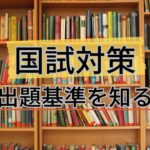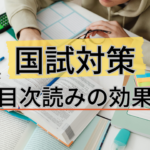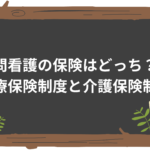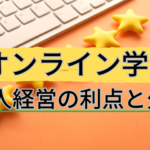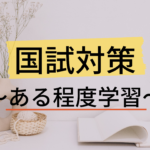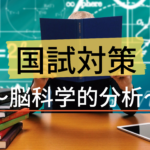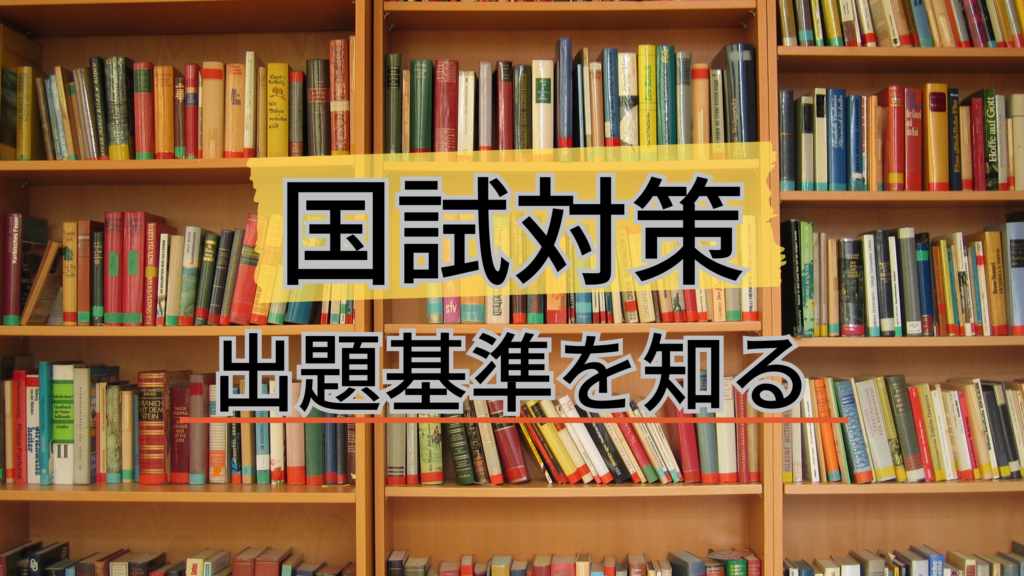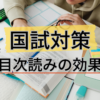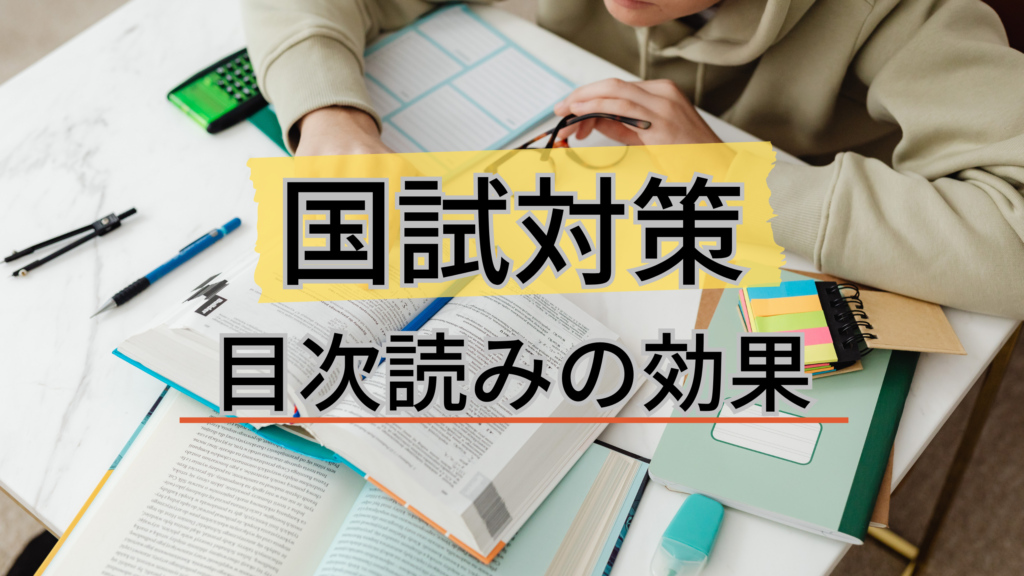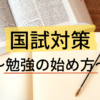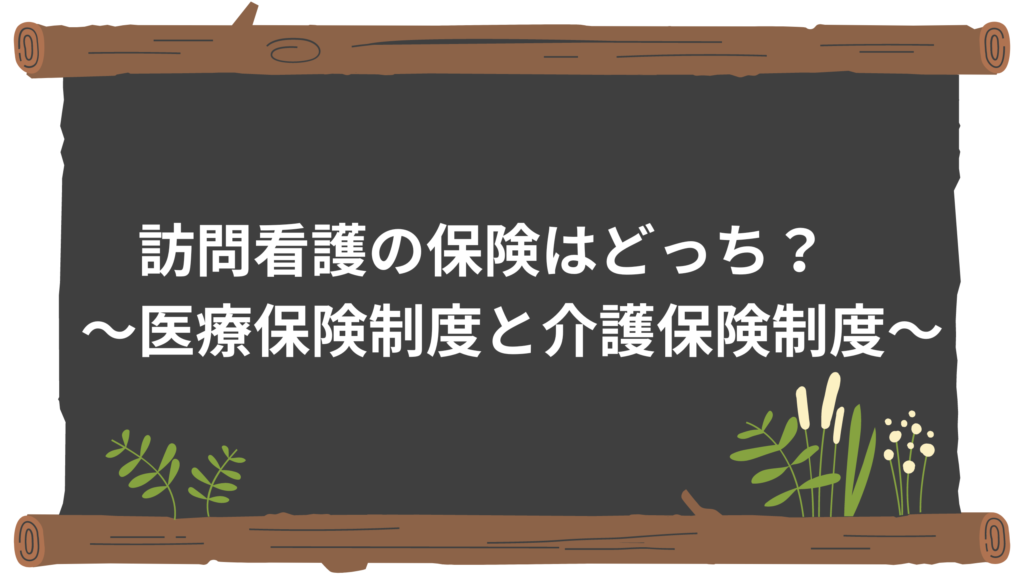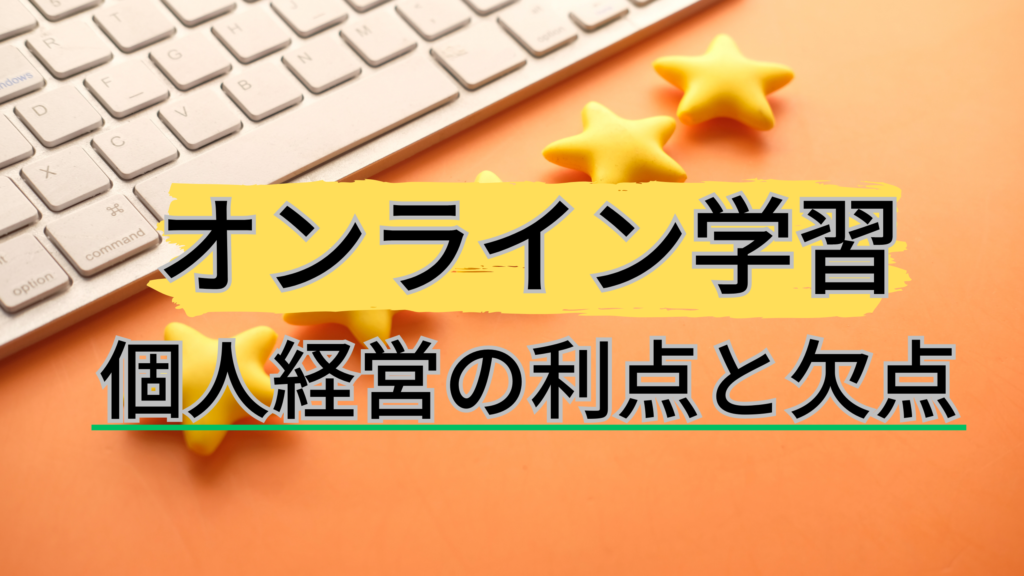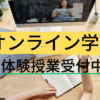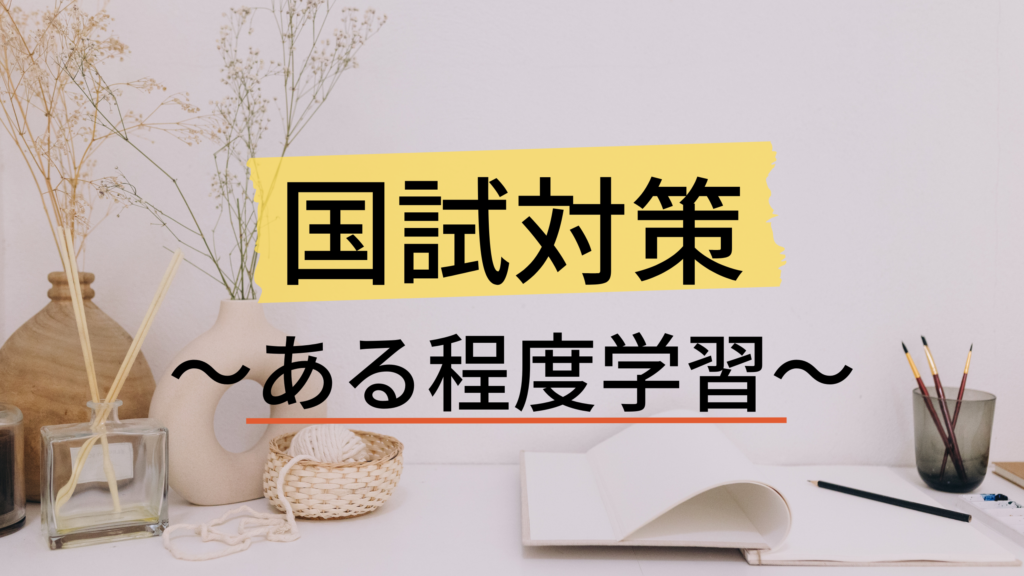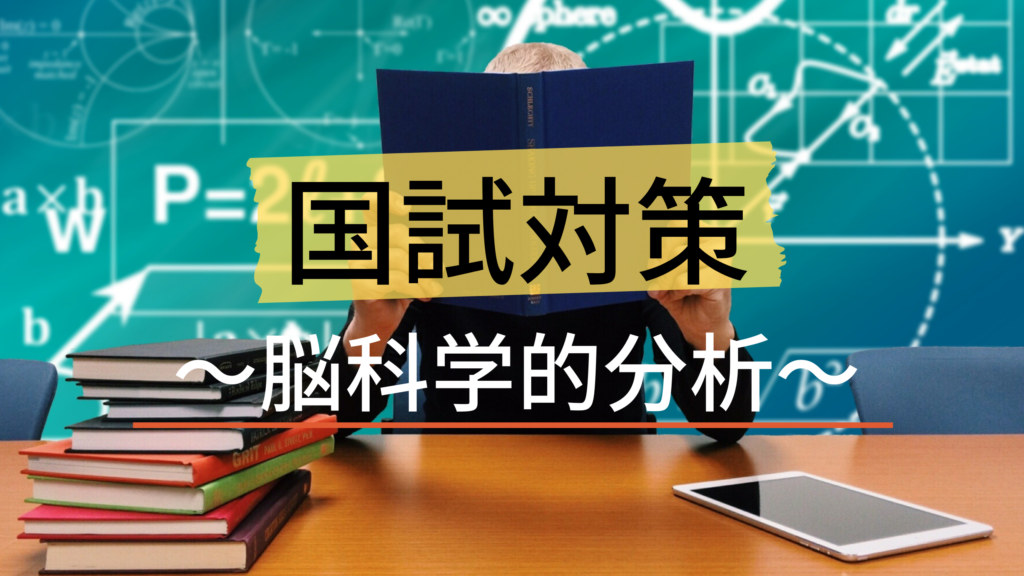こんにちは、講師のサキです。
この記事では、看護師国家試験の出題基準『必修』に焦点を当て、まとめています。
看護師国家試験の出題基準とは、看護師国家試験におけるテスト範囲のようなものです。
定期試験の場合は、必ずテスト範囲を確認して試験に臨むはずです。
これは、無駄な勉強をしたくない、効率良くテスト範囲だけを勉強したい、というような心の現れだと思います。
国家試験においても同様で、出題範囲を理解することで、何を優先的に勉強したら良いのかが分かったり、どの内容の理解が不十分なのかが分かったりします。
出題基準を無視して学習を進める方もいますが、上記の理由で、出題基準を必ず確認してもらうようにしています。
一般問題・状況設定問題にも出題基準はありますが、かなり広範囲になりますので、まずは必修問題の出題基準を把握することから始めることをおすすめします。
こちらの記事には目次読みの大切さを記載していますので、合わせてご確認ください。
必修問題出題基準の4つの大目標
目標Ⅰ.看護の社会的側面及び倫理的側面について基本的な理解を問う。
小項目:1~5
目標Ⅱ.看護の対象者及び看護活動の場について基本的な理解を問う。
小項目:6~9
目標Ⅲ.看護に必要な人体の構造と機能及び健康障害と回復について基本的な理解を問う。
小項目:10~12
目標Ⅳ.看護技術の基本的な理解を問う
小項目:13~16
4つの大目標を理解するために、16の小項目が設定され、さらに16の小項目を理解するための細項目が設定されています。
例)1.健康に関する指標を理解するために、A.人口動態・人口静態やB.健康状態や受療状況などを理解する必要がある。
小項目や細項目を確認することで、国家試験で出題されている問題の意図などが分かってくるかと思います。
では、大目標ごとに小項目を見ていきます。
目標Ⅰ:看護の社会的側面及び倫理的側面について基本的な理解を問う
大目標Ⅰは基本的に社会保障の内容です。社会保障の割合は高いので、10問程度は社会保障の内容が出題されます。
※過去に国家試験に出題された問題や類題の一例を細項目にリンクをつけています。どのような問題が出題されるのか、確認しておきましょう。
|
1. 健康に関する指標
|
A.人口静態・人口動態
|
a.総人口 |
| b.年齢別人口 | ||
| c.労働人口 | ||
| d.将来推計人口 | ||
| e.世帯数 | ||
| f.婚姻・家族形態 | ||
| g.出生の動向 | ||
| h.死亡の動向 | ||
| i.死因の概要 | ||
|
B.健康状態と受療状況
|
a.平均余命 | |
| b.有訴者の状況 | ||
| c.有病率・罹患率 | ||
| d.受療行動・受療率 | ||
| e.入院期間 | ||
| f.外来受診状況 | ||
|
2.健康と生活
|
A.生活行動・習慣
|
a.食事・栄養 |
| b.睡眠 | ||
| c.運動 | ||
| d.代謝障害 | ||
| e.喫煙 | ||
| f.ストレス | ||
| g.メンタルヘルス | ||
| h.ライフスタイル | ||
| i.性行動 | ||
|
B.労働
|
a.職業と疾病 | |
| b.労働環境 | ||
| c.雇用形態 | ||
| d.母性保護と両立支援 | ||
|
C.生活環境
|
a.水・空気・土壌 | |
| b.食品衛生 | ||
| c.住環境・社会環境 | ||
|
3.保健医療制度の基本
|
A.医療保険制度
|
a.医療保険の種類 |
| b.国民皆保険 | ||
| c.国民医療費 | ||
| d.高齢者医療制度 | ||
| e.給付の内容 | ||
|
B.介護保険制度
|
a.保険者 | |
| b.被保険者 | ||
| c.給付の内容 | ||
| d.要介護認定 | ||
|
4.看護の倫理
|
A.基本的人権の擁護
|
a.個人の尊厳 |
| b.患者の権利 | ||
| c.自己決定権と患者の意思 | ||
| d.インフォームド・コンセント | ||
| e.ノーマライゼーション | ||
| f.情報管理(個人情報保護法) | ||
|
B.看護倫理
|
a.看護職の役割 | |
| b.看護の倫理綱領 | ||
|
5.関係法規
|
A.保健師助産師看護師法
|
a.保健師助産師看護師の業務 |
| b.看護師に禁止されている業務 | ||
| c.秘密の保持(守秘義務) | ||
|
B.看護師等の人材確保の促進に関する法律
|
a.基本方針 | |
| b.養成制度 | ||
| c.就業状況 |
目標Ⅱ:看護の対象者及び看護活動の場について基本的な理解を問う
目標Ⅱは看護学概論や理論の基礎知識や社会保障の分野になります。
ここでも社会保障の内容が入っています。どちらかというと目標Ⅰ・Ⅱは暗記が主体になります。
|
6.人間の特性
|
A.人間と欲求
|
a.基本的欲求 |
| b.社会的欲求 | ||
|
B.患者の特性
|
a.QOL | |
| b.患者ニーズ | ||
| c.健康に対する意識 | ||
| d.疾病に対する意識 | ||
| e.疾病・障害の受容 | ||
|
7.人間の成長と発達
|
A.胎児期
|
a.形態的発達 |
| b.先天異常 | ||
| c.胎児期の異常 | ||
|
B.新生児期・乳児期
|
a.発達の原則 | |
| b.身体の発育 | ||
| c.運動能力の発達 | ||
| d.栄養 | ||
| e.親子関係 | ||
| f.先天免疫と獲得免疫 | ||
|
C.幼児期
|
a.身体の発育 | |
| b.運動能力の発達 | ||
| c.排泄の自立 | ||
| d.言語発達 | ||
| e.社会性の発達 | ||
| f.基本的生活習慣の確立 | ||
|
D.学童期
|
a.運動能力・体力の特徴 | |
| b.社会性の発達 | ||
| c.学習に基づく行動 | ||
|
E.思春期
|
a.第二次性徴 | |
| b.アイデンティティの確立 | ||
| c.親からの自立 | ||
| d.異性への関心 | ||
|
F.成人期
|
a.社会的責任と役割 | |
| b.生殖機能の成熟と衰退 | ||
| c.基礎代謝の変化 | ||
|
G.老年期
|
a.運動能力・体力の変化 | |
| b.知覚・感覚の変化 | ||
| c.認知能力の変化 | ||
| d.心理社会的変化 | ||
| e.個別性・多様性 | ||
|
8.患者と家族
|
A.家族の機能
|
a.家族関係 |
| b.家族構成員 | ||
|
B.家族形態の変化
|
a.家族の多様性 | |
| b.構成員の変化 | ||
| c.疾病が患者・家族に与える心理社会的影響 | ||
|
9.主な看護活動展開の場と看護の機能
|
A.医療提供施設
|
a.病院 |
| b.診療所 | ||
| c.助産所 | ||
| d.介護老人保健施設 | ||
|
B.保健所・市町村における看護活動
|
a.保健所の業務 | |
| b.市町村の業務 | ||
|
C.地域・在宅での看護
|
a.居宅 | |
| b.訪問看護ステーション | ||
| c.介護保険施設 | ||
| d.地域包括支援センター | ||
|
D.看護管理
|
a.看護体制 | |
| b.看護チーム | ||
| c.安全管理<セーフティマネジメント> | ||
| d.インシデントレポート | ||
|
E.関連職種との連携
|
a.関連する職種 | |
| b.チーム医療 | ||
| c.看護の役割 |
目標Ⅲ:看護に必要な人体の構造と機能及び健康障害と回復について基本的な理解を問う
目標Ⅲは、解剖生理・病態生理・薬理学といった内容です。
この範囲は理解が必要になり、難しい範囲です。一般問題とも密接に関係してくるので、一般と合わせて理解していくことが重要です。
|
10.生命活動
|
A.人体の構造と機能
|
a.内部環境の恒常性<ホメオスタシス> |
| b.血液・水・電解質 | ||
| c.体温 | ||
| d.感染防御と免疫反応 | ||
| e.循環器系 | ||
| f.呼吸器系 | ||
| g.神経系 | ||
| h.消化器系 | ||
| i.泌尿器系 | ||
| j.代謝・内分泌系 | ||
| k.骨・筋系 | ||
| l.性と生殖器系 | ||
| m.遺伝 | ||
|
B.正常な妊娠・分娩・産褥
|
a.妊娠の成立 | |
| b.妊娠の経過 | ||
| c.分娩の経過 | ||
| d.産褥の経過 | ||
|
C.人間の死
|
a.死の三徴候 | |
| b.死亡判定 | ||
| c.脳死 | ||
| d.死の受容 | ||
|
11.病態と看護
|
A.症状と看護
|
a.意識障害 |
| b.ショック | ||
| c.高体温・低体温 | ||
| d.脱水 | ||
| e.黄疸 | ||
| f.頭痛 | ||
| g.咳嗽・喀痰 | ||
| h.吐血・喀血 | ||
| i.チアノーゼ | ||
| j.呼吸困難 | ||
| k.胸痛 | ||
| l.不整脈 | ||
| m.腹痛・腹部膨満 | ||
| n.嘔気・嘔吐 | ||
| o.下痢 | ||
| p.便秘 | ||
| q.下血 | ||
| r.乏尿・無尿・頻尿 | ||
| s.浮腫 | ||
| t.貧血 | ||
| u.睡眠障害 | ||
| v.感覚の異常 | ||
| w.運動の異常(麻痺・失調) | ||
| x.けいれん | ||
|
B.主要疾患と看護
|
a.生活習慣病 | |
| b.がん | ||
| c.感染症 | ||
| d.外因性障害 | ||
| e.精神疾患 | ||
| f.小児疾患 | ||
| g.高齢者の疾患 | ||
|
12.薬物治療に伴う反応
|
A.主な薬物の作用と副作用
|
a.抗菌薬 |
| b.抗ウイルス薬 | ||
| c.抗癌薬 | ||
| d.強心薬・抗不整脈薬 | ||
| e.狭心症治療薬 | ||
| f.降圧薬・昇圧薬 | ||
| g.利尿薬 | ||
| h.副腎皮質ステロイド | ||
| i.糖尿病治療薬 | ||
| j.中枢神経作用薬 | ||
| k.麻薬 | ||
| l.消炎鎮痛薬 | ||
|
B.医薬品の安全対策
|
a.混合の可否 | |
| b.禁忌 | ||
| c.保存方法 | ||
| d.薬理効果に影響する要因 |
目標Ⅳ:看護技術の基本的な理解を問う
目標Ⅳは看護技術の基礎的な内容になります。
この範囲は看護技術なので、どちらかというと暗記で、考えると分かる問題も多いです。ただ、決しておろそかにせずに正確な値などを覚えることが大切です。
|
13.基本技術
|
A.コミュニケーション
|
a.言語的コミュニケーション |
| b.非言語的コミュニケーション | ||
| c.面接技法 | ||
|
B.フィジカルアセスメント
|
a.バイタルサインの測定と評価 | |
| b.意識レベルの評価 | ||
| c.呼吸音聴取の方法と評価 | ||
| d.腸蠕動音聴取の方法と評価 | ||
| e.運動系の観察と評価 (ADL・ROM・MMT) | ||
|
C.看護過程
|
a.情報収集 | |
| b.アセスメント | ||
| c.計画立案 | ||
| d.実施 | ||
| e.評価 | ||
| f.記録 | ||
|
14.日常生活援助技術
|
A.食事
|
a.食事の環境 |
| b.食事介助の方法 | ||
| c.誤嚥の予防 | ||
|
B.排泄
|
a.床上排泄 | |
| b.導尿 | ||
| c.浣腸 | ||
| d.摘便 | ||
| e.失禁のケア | ||
|
C.清潔
|
a.入浴 | |
| b.清拭 | ||
| c.口腔ケア | ||
| d.洗髪 | ||
| e.部分浴 | ||
| f.陰部洗浄 | ||
| g.整容 | ||
| h.寝衣交換 | ||
|
D.活動と休息
|
a.睡眠 | |
| b.体位 | ||
| c.体位変換 | ||
| d.移動・移送 | ||
| e.ボディメカニクス | ||
| f.廃用症候群の予防 | ||
|
15.患者の安全・安楽を守る技術
|
A.療養環境
|
a.病室環境 |
| b.共有スペース | ||
| c.居住スペース | ||
|
B.医療安全対策
|
a.転倒・転落の防止 | |
| b.誤薬の防止 | ||
| c.患者誤認の防止 | ||
| d.誤嚥・窒息の防止 | ||
| e.情報伝達と共有・管理 | ||
|
C.院内感染防止対策
|
a.スタンダードプリコーション | |
| b.手洗いの方法 | ||
| c.無菌操作 | ||
| d.滅菌と消毒の方法 | ||
| e.針刺し・切創の防止 | ||
| f.感染性廃棄物の取り扱い | ||
|
16.診療に伴う看護技術
|
A.栄養補給
|
a.経管栄養法 |
| b.経静脈栄養法 | ||
|
B.薬物療法
|
a.与薬方法 | |
| b.薬効・副作用(有害事象)の観察 | ||
|
C.輸液管理
|
a.刺入部位の観察 | |
| b.輸液ポンプの取り扱い | ||
| c.点滴静脈内注射の管理 | ||
|
D.採血
|
a.穿刺部位 | |
| b.採血方法 | ||
|
E.罨法
|
a.罨法の種類と適応 | |
| b.温罨法の方法 | ||
| c.冷罨法の方法 | ||
|
F.呼吸管理
|
a.酸素吸入時の原則 | |
| b.酸素ボンベの取り扱い | ||
| c.酸素流量計の取り扱い | ||
| d.鼻腔カニューラ | ||
| e.酸素マスク | ||
| f.ネブライザー | ||
|
G.吸引
|
a.口腔内・鼻腔内吸引 | |
| b.気管内吸引 | ||
| c.体位ドレナージ | ||
|
H.救命救急処置
|
a.気道の確保 | |
| b.人工呼吸 | ||
| c.心マッサージ | ||
| d.直流除細動器 | ||
| e.自動体外式除細動器<AED> | ||
| f.止血 | ||
| g.体温の保持・冷却 | ||
|
I.皮膚・創傷の管理
|
a.包帯法 | |
| b.創傷の管理 | ||
| c.褥瘡の予防・処置 | ||
|
J.災害看護
|
a.トリアージ | |
| b.応急処置の原則 | ||
| c.搬送・移送 | ||
| d.こころのケア |
まとめ
・必修問題は、4つの大目標と16の小項目に基づいて出題される。
・定期試験の範囲を確認するように、必修問題の出題範囲を確認し、優先的に勉強した方が良いことや、理解不十分な内容を自分で分かるようにする。
・目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅳはどちらかというと暗記が中心。
・目標Ⅲは理解が必要になる。一般問題などと合わせて理解を進めることが重要。
今解いている問題、解こうとしている問題が、出題基準に照らすとどの範囲なのか、解けない問題はどの範囲なのか、自分の理解度を知ることが大切です。