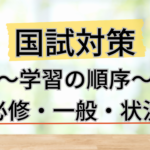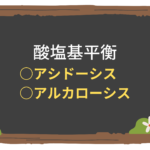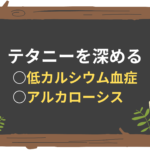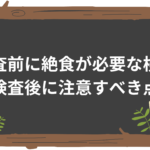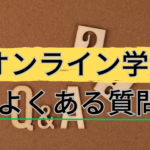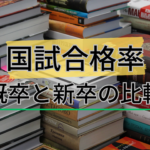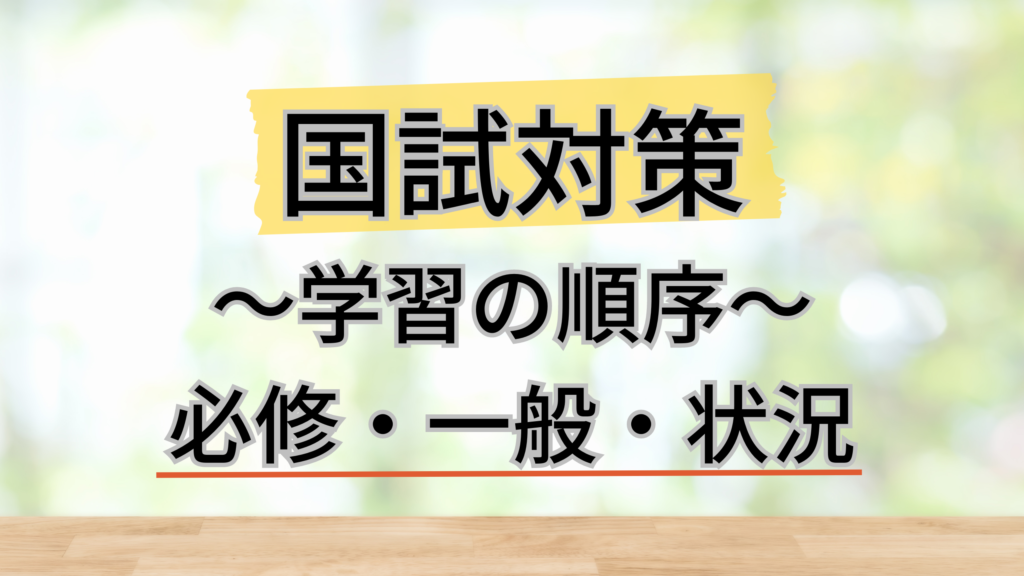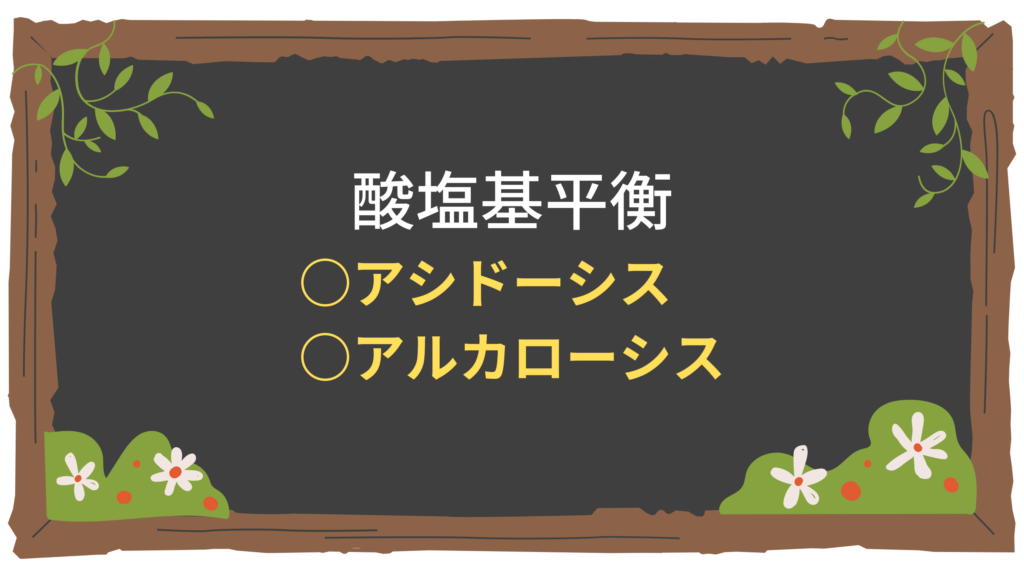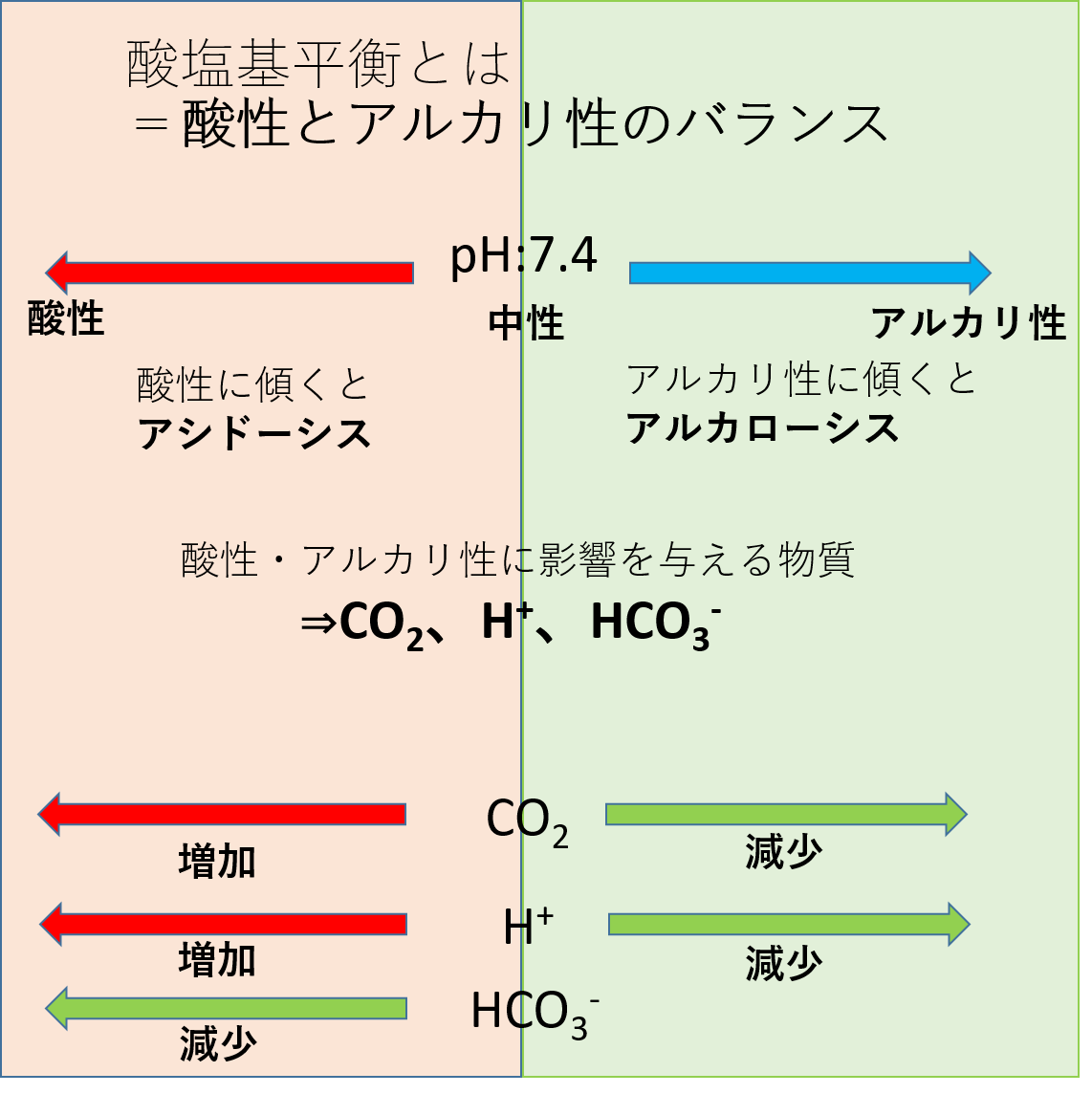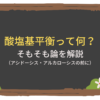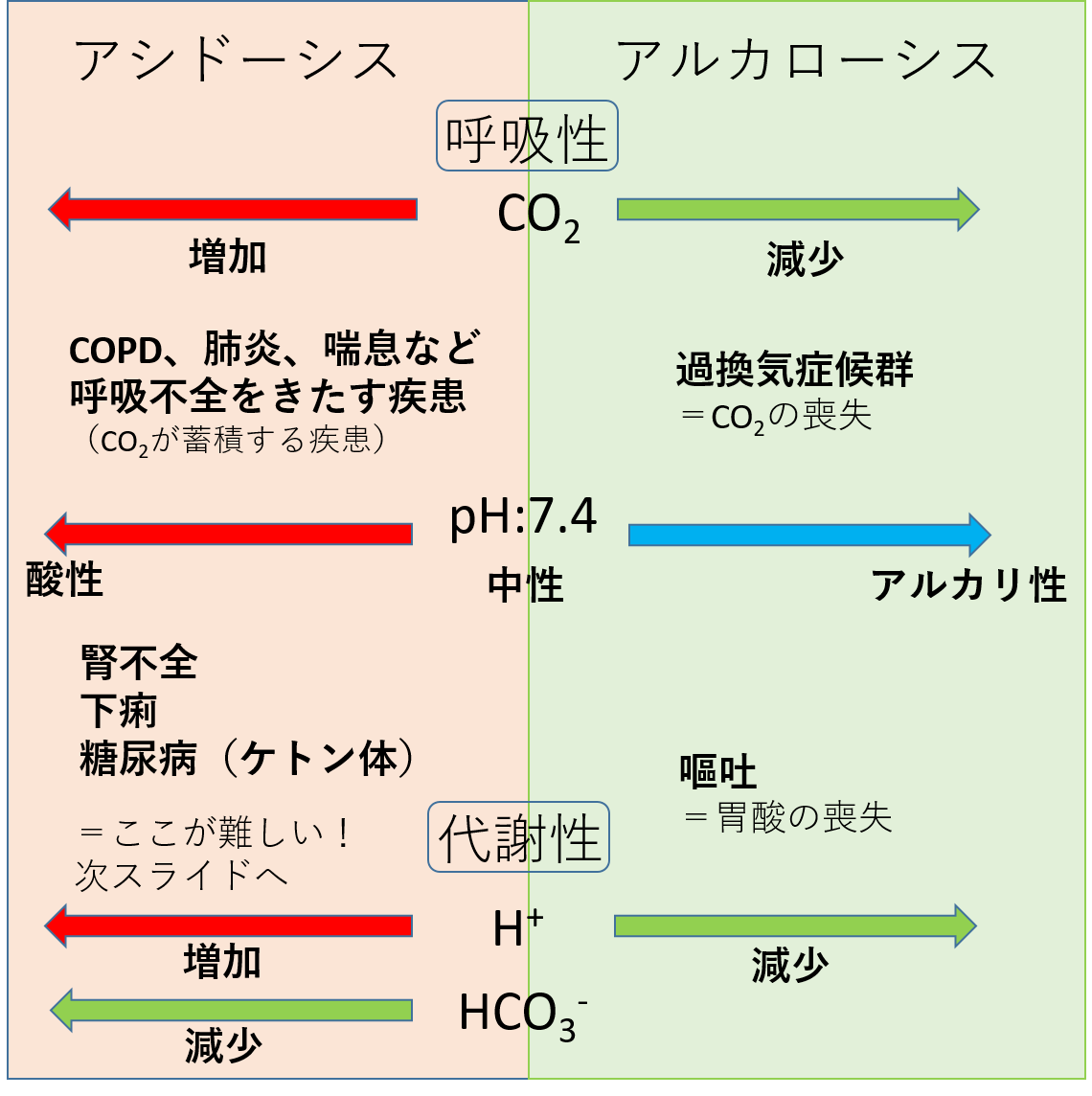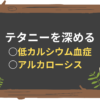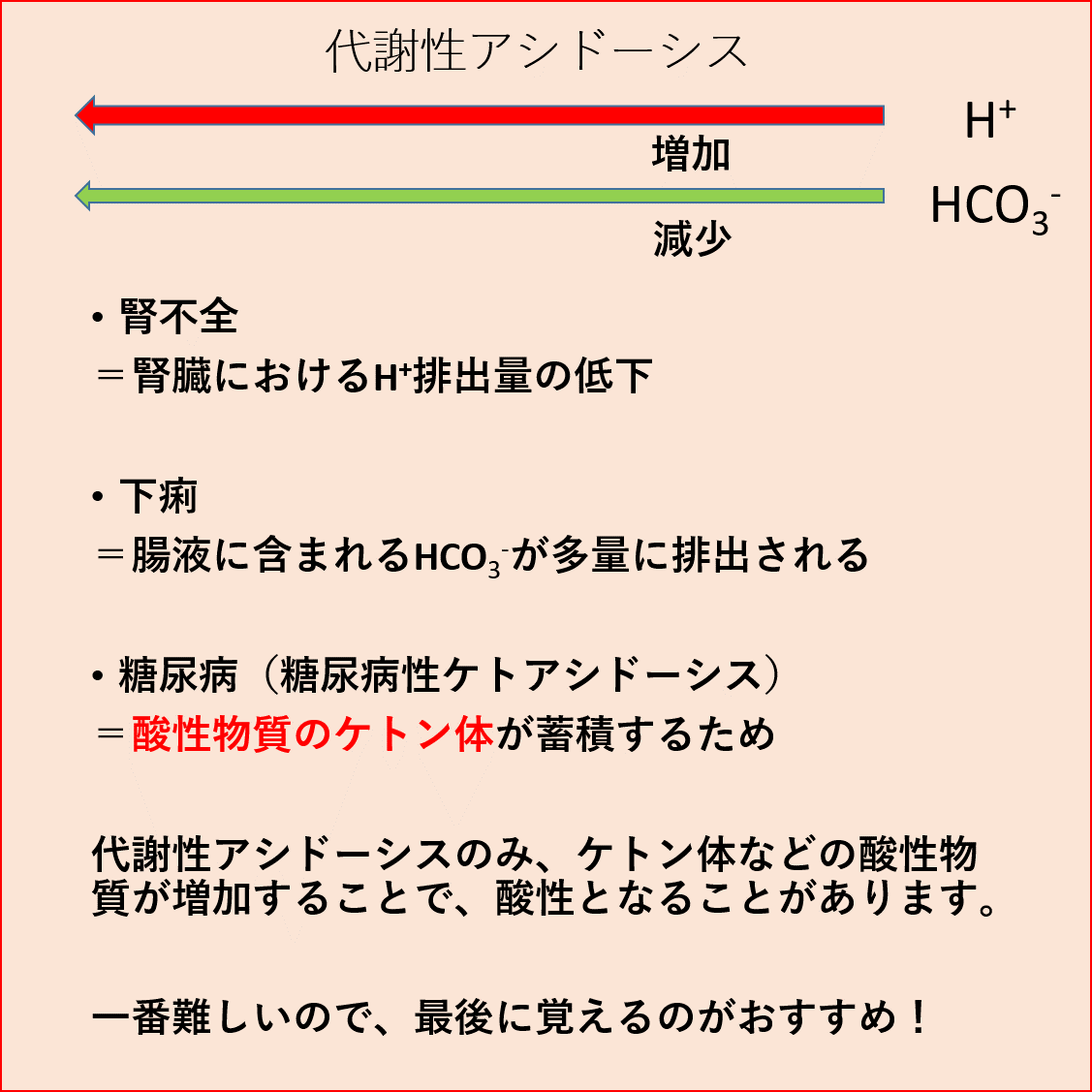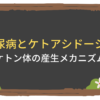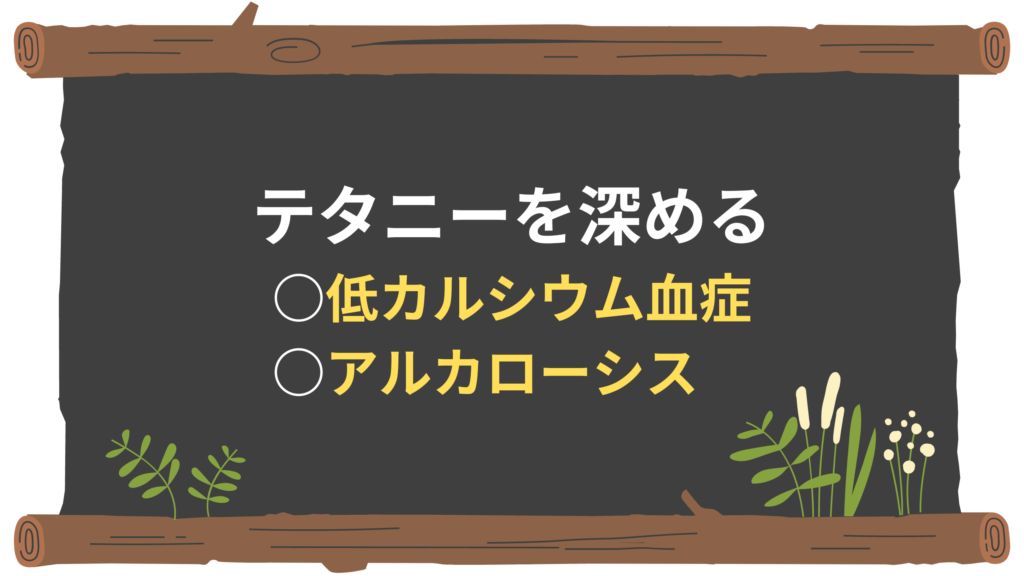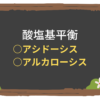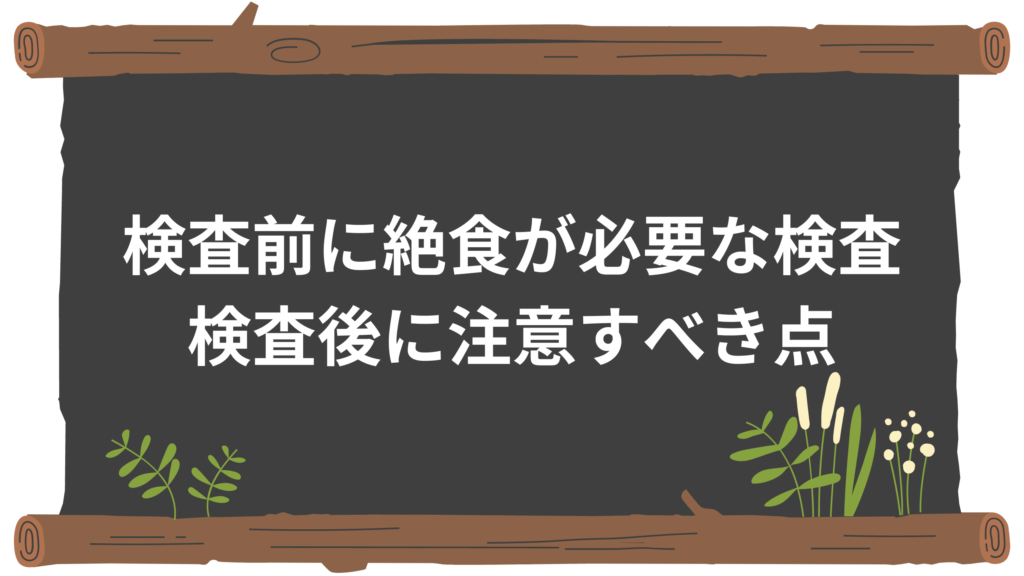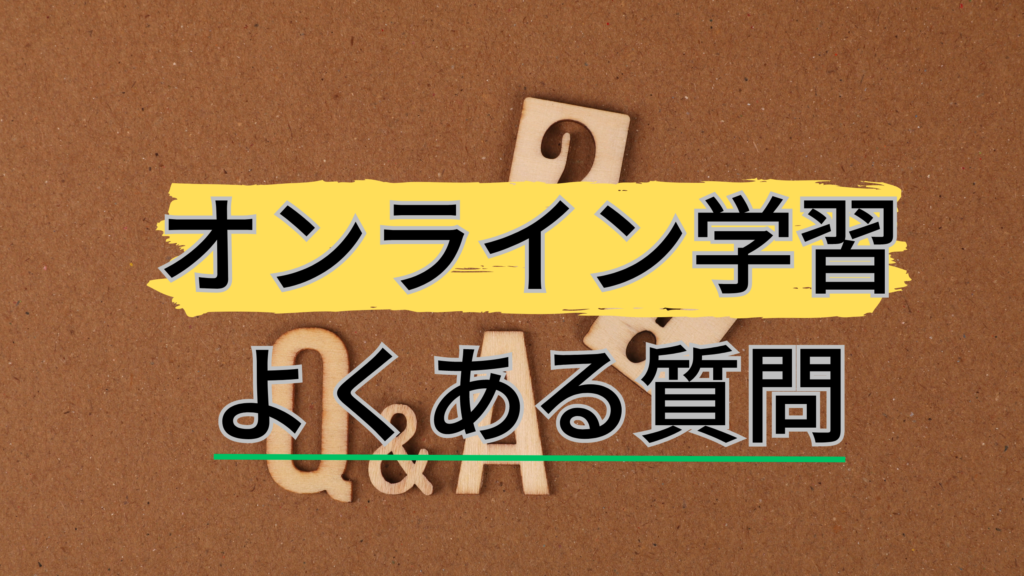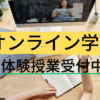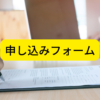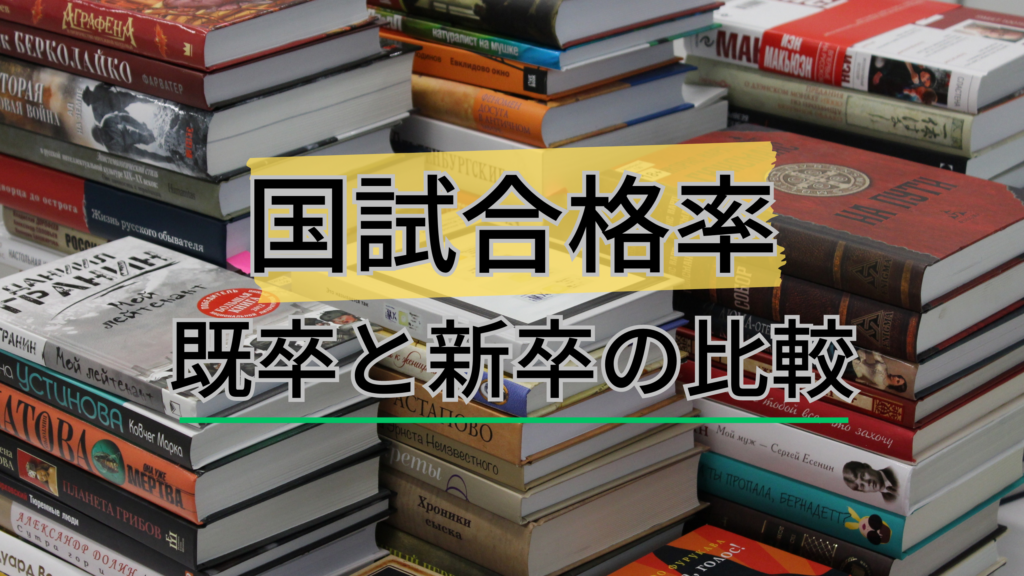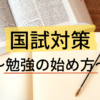こんにちは、講師のサキです。
この記事では、看護師国家試験の勉強では、必修・一般・状況設定問題、どこから手を付けることが効率が良いのか、ということを説明していきます。
先に結論を述べると、『必修問題』からが最も効率の良い順番になります。
必ずという訳ではありませんが、今から理由をお伝えしていきますので、ご興味を持たれたら、とりあえず必修から進めてみて下さい。
必修問題の重要性
そもそも必修問題は別格に取り扱われている問題です。
配点は、必修問題:50点、一般問題:130点、状況設定問題:120点の合計300点満点で国家試験は作成されます。
必修問題の配点は少ないように見えますが、50点中40点をとれなかった場合、一般・状況の得点が良かったとしても、そこで不合格となってしまいます。
必修問題の得点がとれずに涙をのむ学生を多数見てきましたので、最初から最後まで解き続けるようにしてください。
何故、必修問題から始めるのか
理由は2つあります。
①必修問題は全ての基礎になるため
基礎的な知識である故に、40点未満の学生を一発不合格にするという基準を設けています。
必修問題が怖いと思う前に、必修問題は全てにつながる重要な知識になると考え、始めから満点をとれるように取り組むことが重要です。
必修問題の学習を一通り進めた後に、一般・状況設定問題の勉強を始めると、基礎知識が多少はできているため、スムーズに学習していけると思います。
②難易度が高くない
先述のとおり、必修問題は基礎知識になりますので、難易度は高くありません。
いきなり一般・状況設定問題に取り組むと、難しさのあまり一気に勉強に対する意欲が低下してしまうことがあります。
学習に対する意欲は高い状態に維持しておくことが重要です。
簡単な問題だとしても解けるということは、学習意欲を高く維持することにつながります。
勉強の始め方や方法に迷った時は、必修問題から始め、全問を覚えてしまうくらいの勢いで、とりあえず突き進んでみてください。
必修問題の出題基準を参考にしながら進める
最初はがむしゃらに突き進むことで良いですが、学習が進むにつれて、自分の学習状況の全体像をつかむことも重要になってきます。
一般問題の範囲を押さえるのはなかなか難しいですが、必修問題であれば、出題基準を活用して、全体像を把握することは可能です。
必修問題の参考書について
最後に参考書ついてです。
参考書はレビューブック、QB一般、QB必修の3点セットをいつもおすすめしています。
必修問題の学習についても、QB必修問題を使って、覚えていくことで問題ありませんが、QB必修問題は基本的に過去問を取り扱っているので、必修問題を完璧にするという意味ではやや不十分な印象もあります。
そのため、QB必修問題集が一通り終わったら、必修問題に特化した問題集を別に1冊くらい購入することをおすすめします。
本屋で実際に手にとって自分に合った問題集が一番良いと思いますが、一応おすすめを
3冊紹介しておきます。
・必修問題2023
・必修問題ファイナルチェック360
・必修ラスパ
過去問に類似した、そしてやや難易度を上げた必修問題集になっていますので、一般・状況設定問題にもつながってくると思います。
ファイナルチェックやラストスパートというような本の名前ですが、最後に使うのではなく、あえて最初に完璧に使い込むという方法もおすすめしています。
まとめ
・国家試験の学習は、必修問題から進める
・必修問題は、基礎的ながら重要な内容なので、意欲的に効率良く取り組むことができ、一般・状況設定問題の学習にもつながる
・必修問題は過去問だけでなく、やや難易度が高い内容の問題集を使い、最初から完璧にしてしまうこともおすすめ