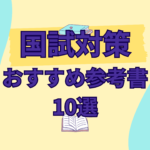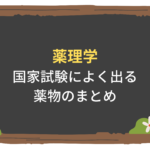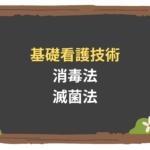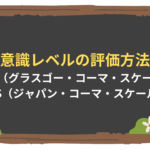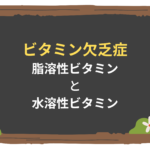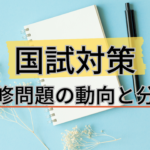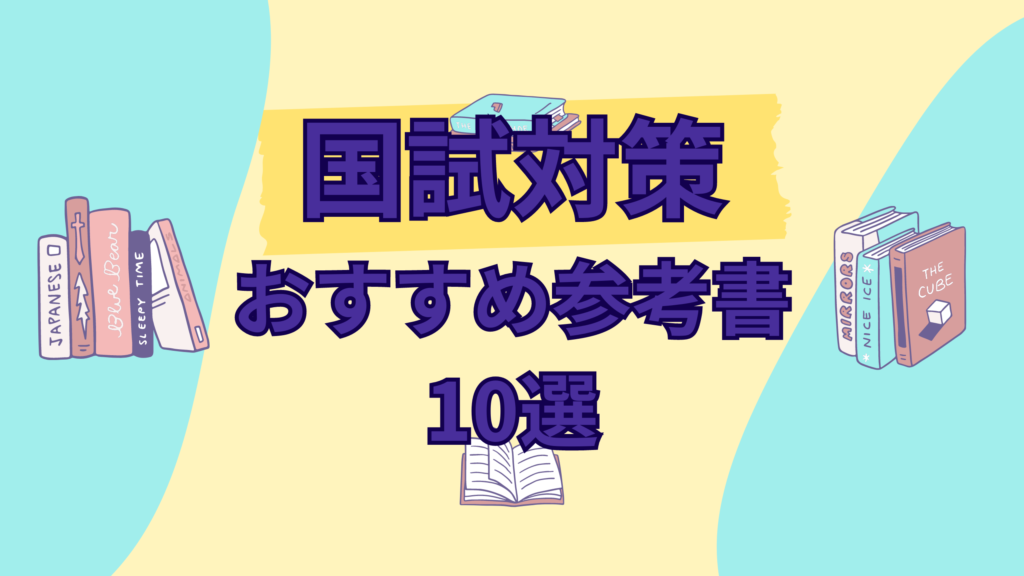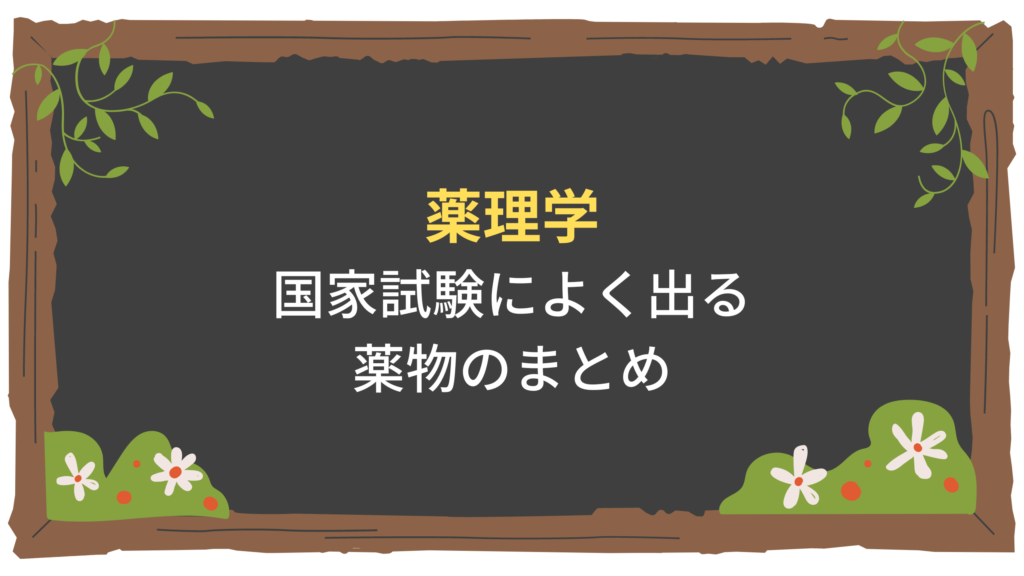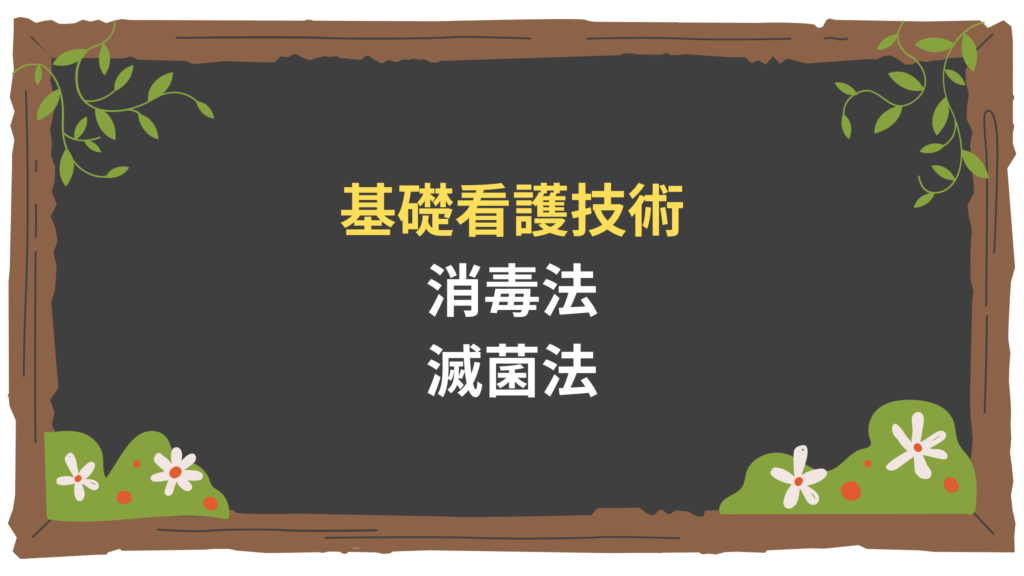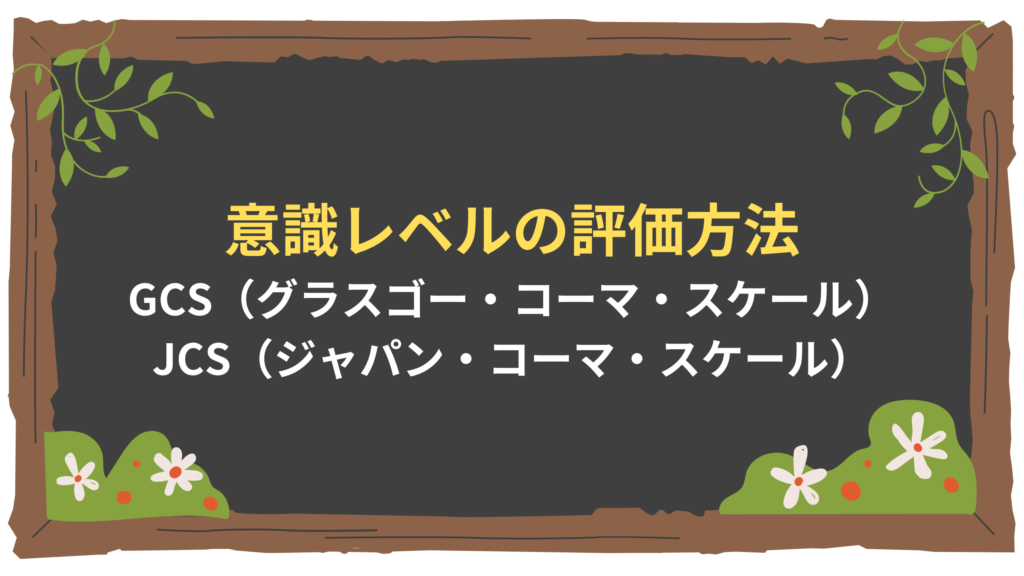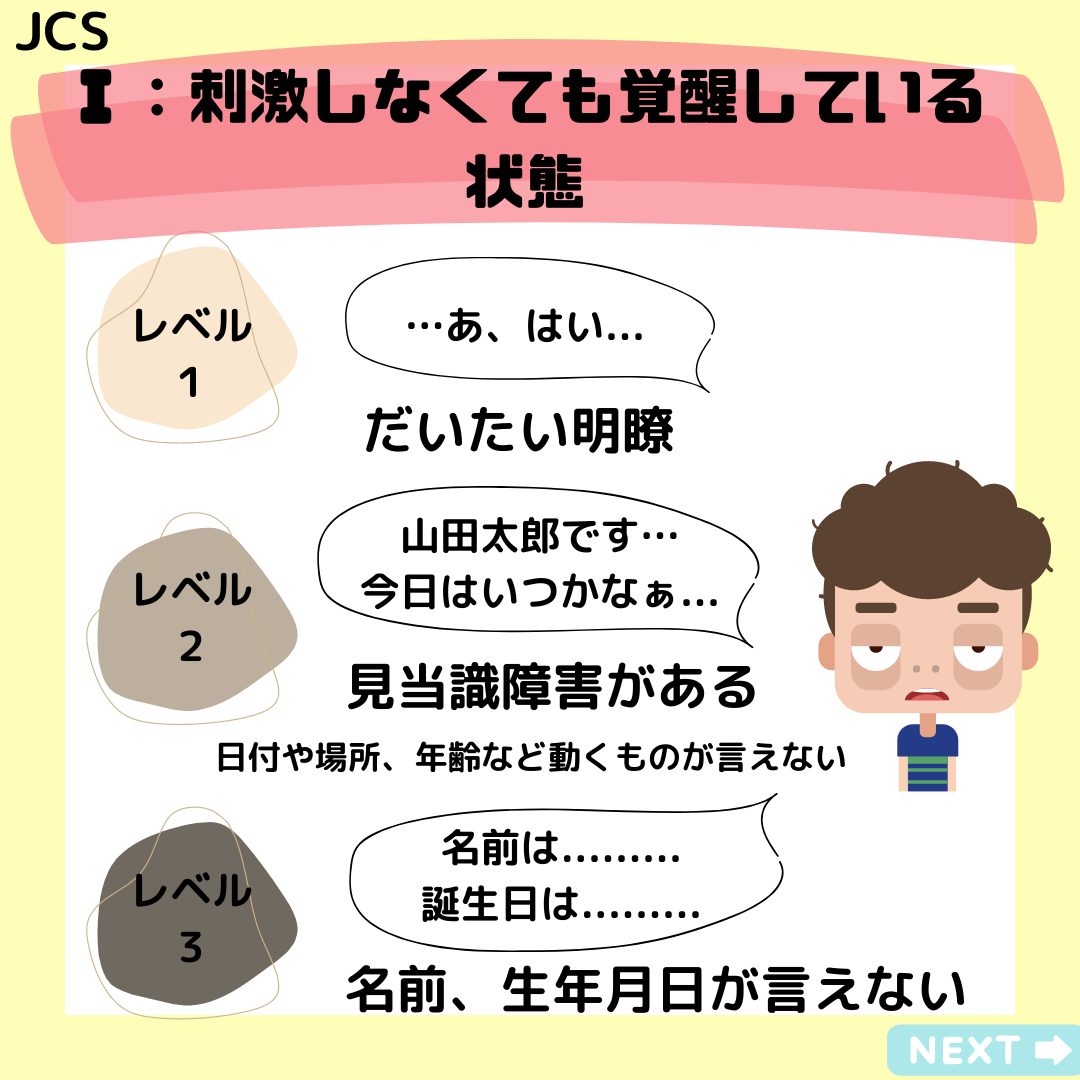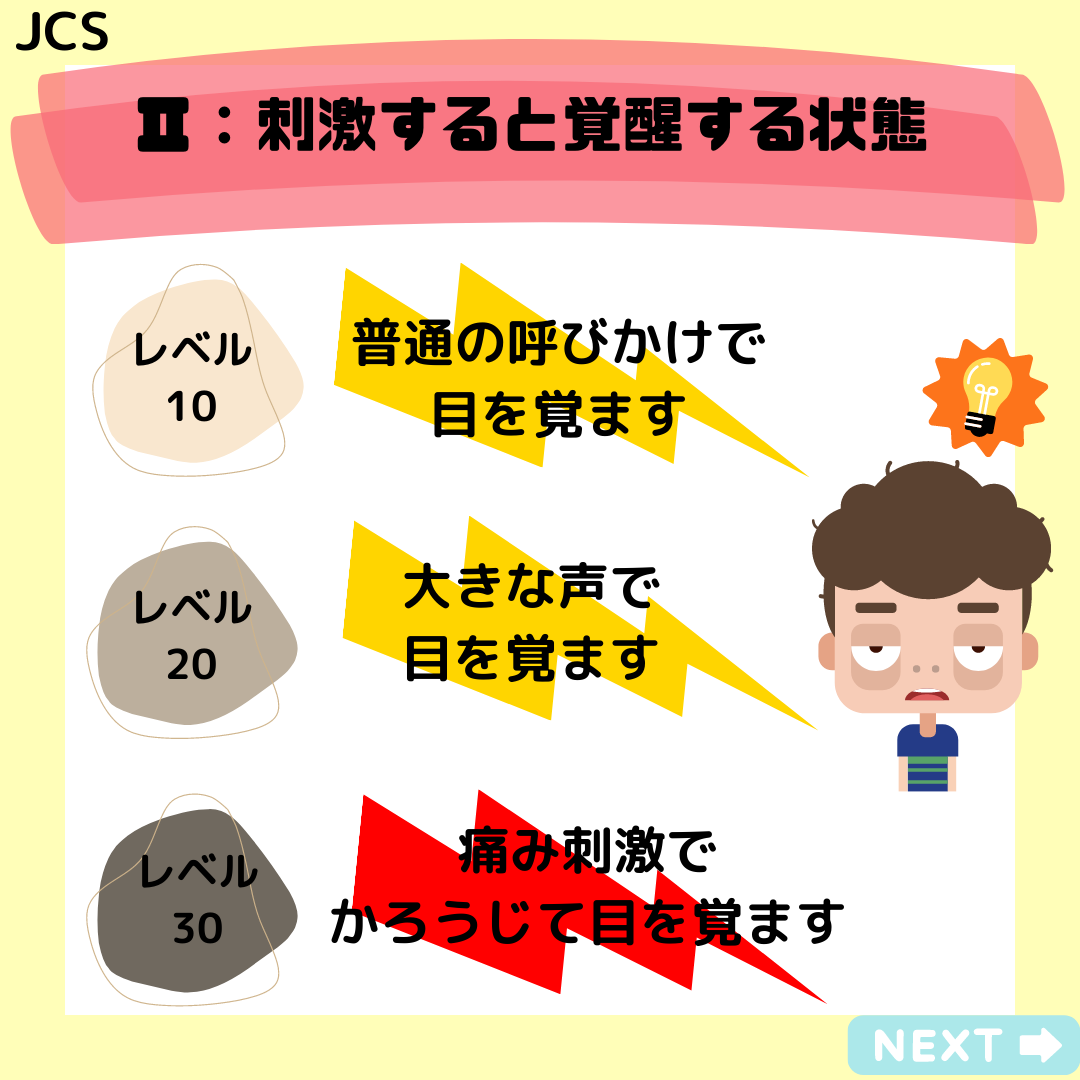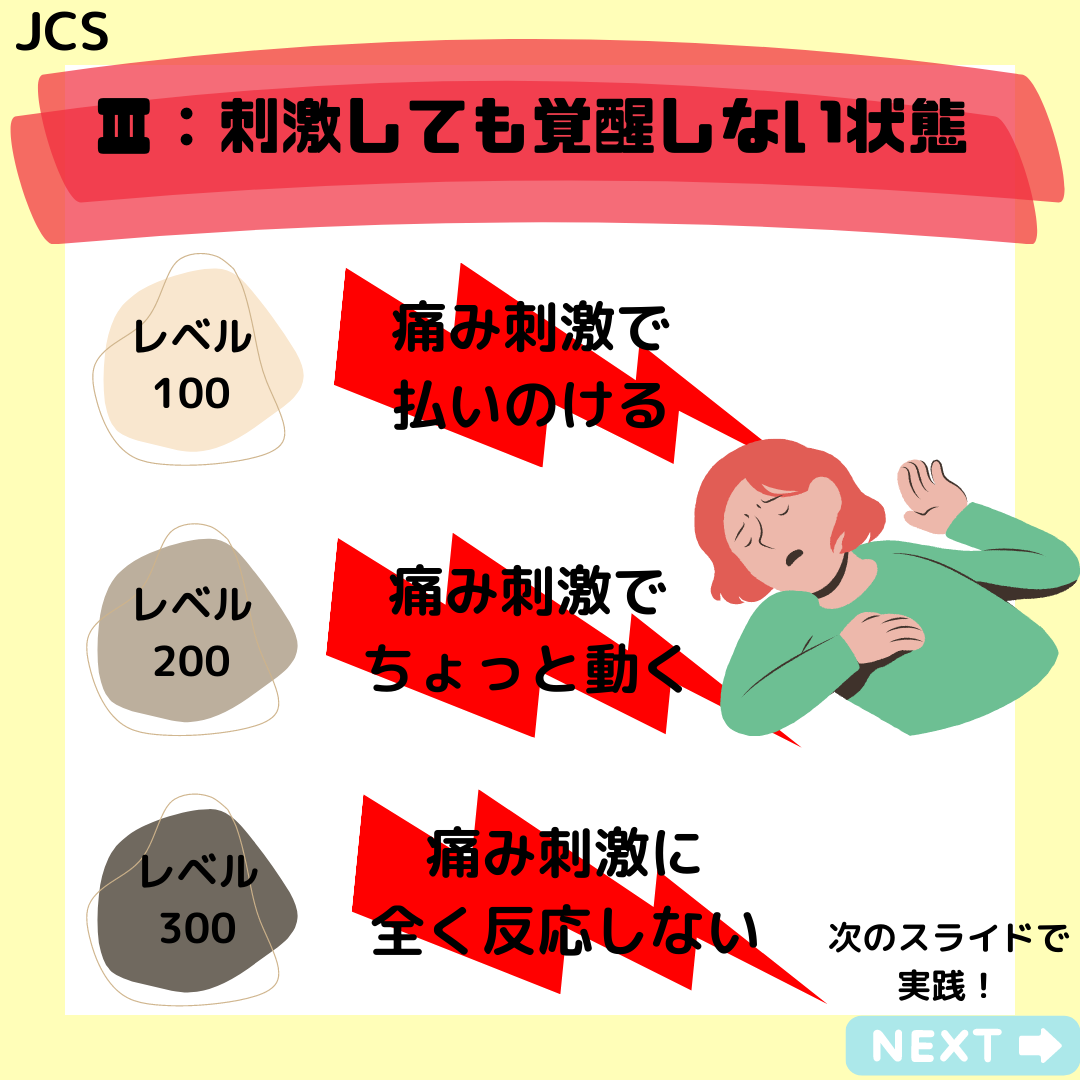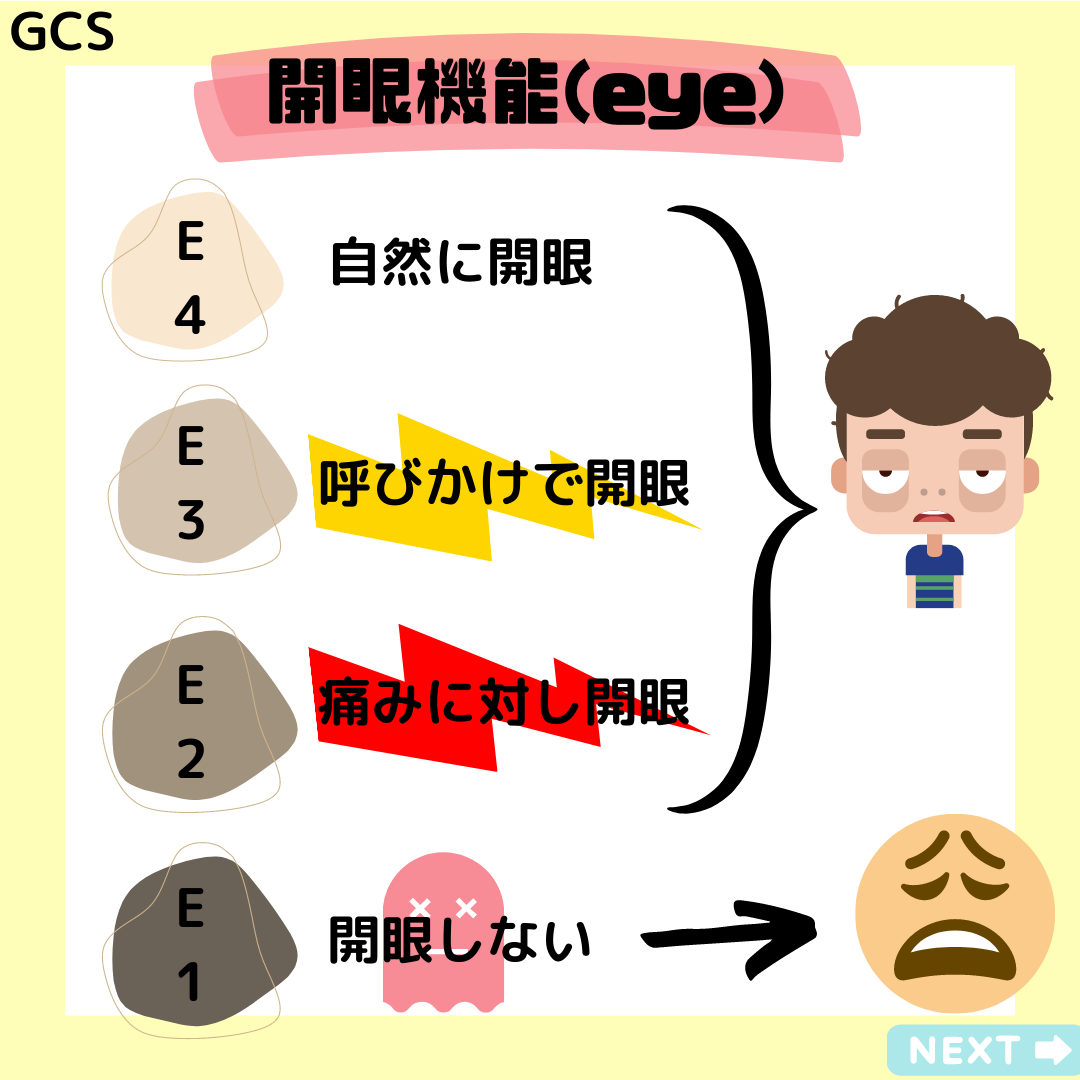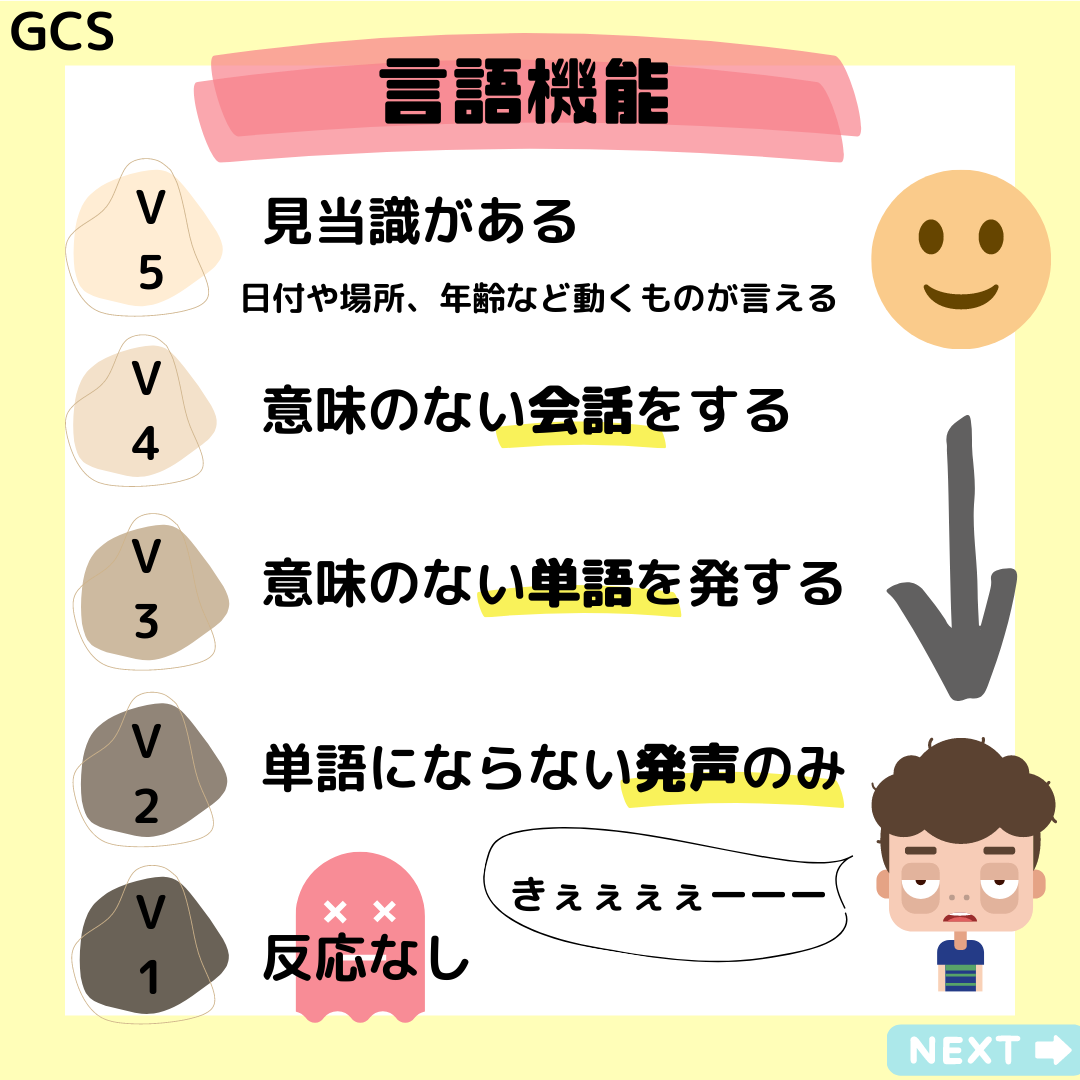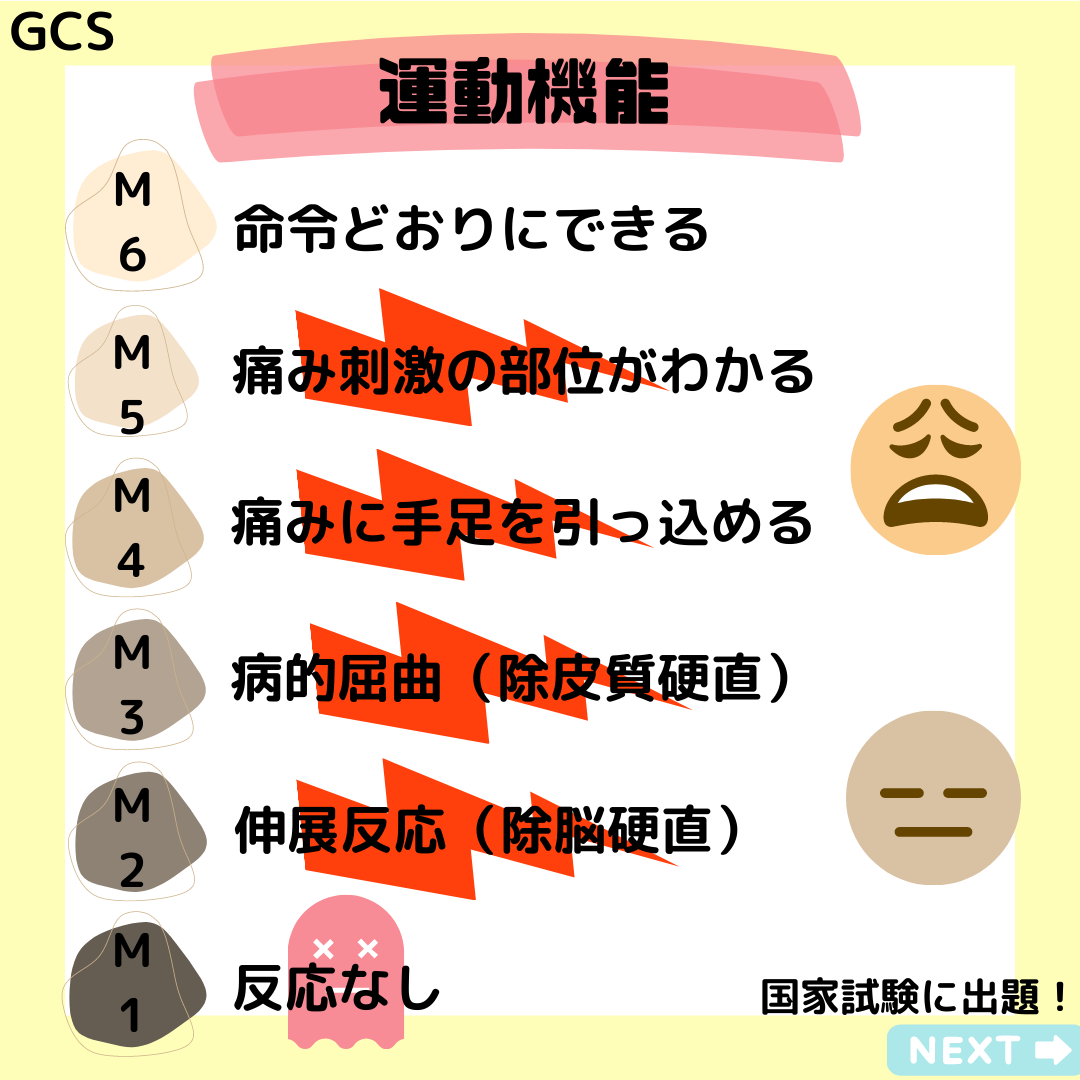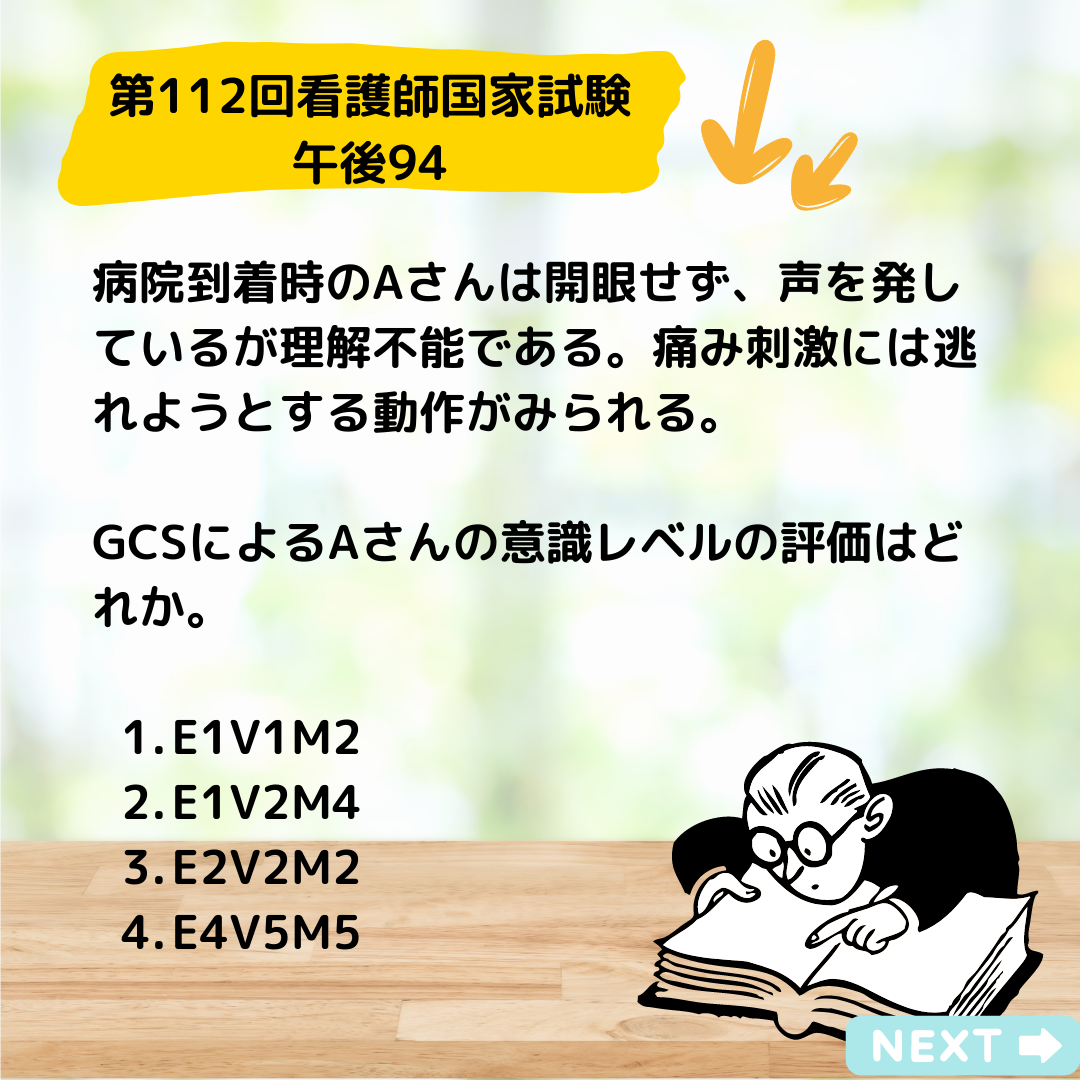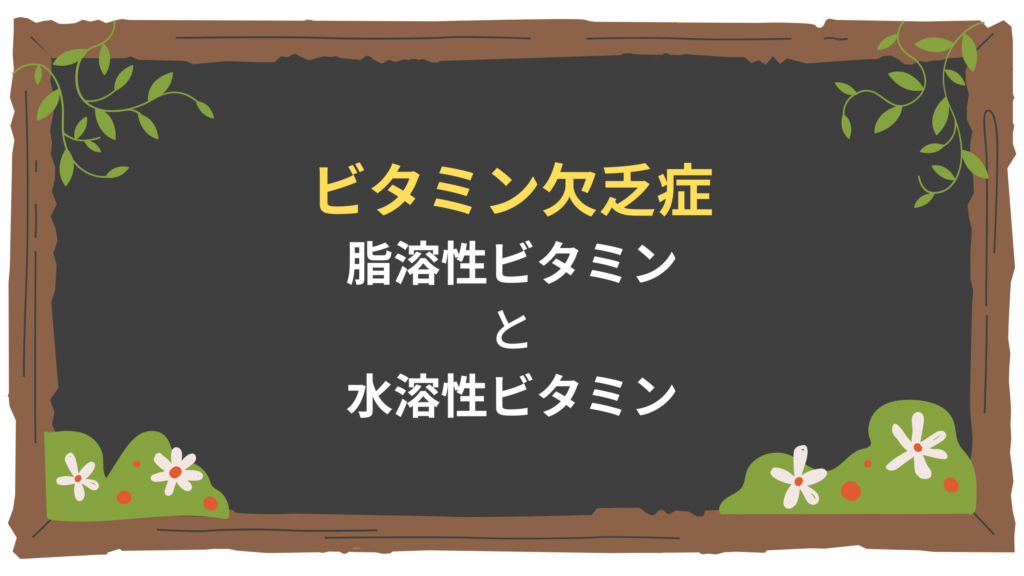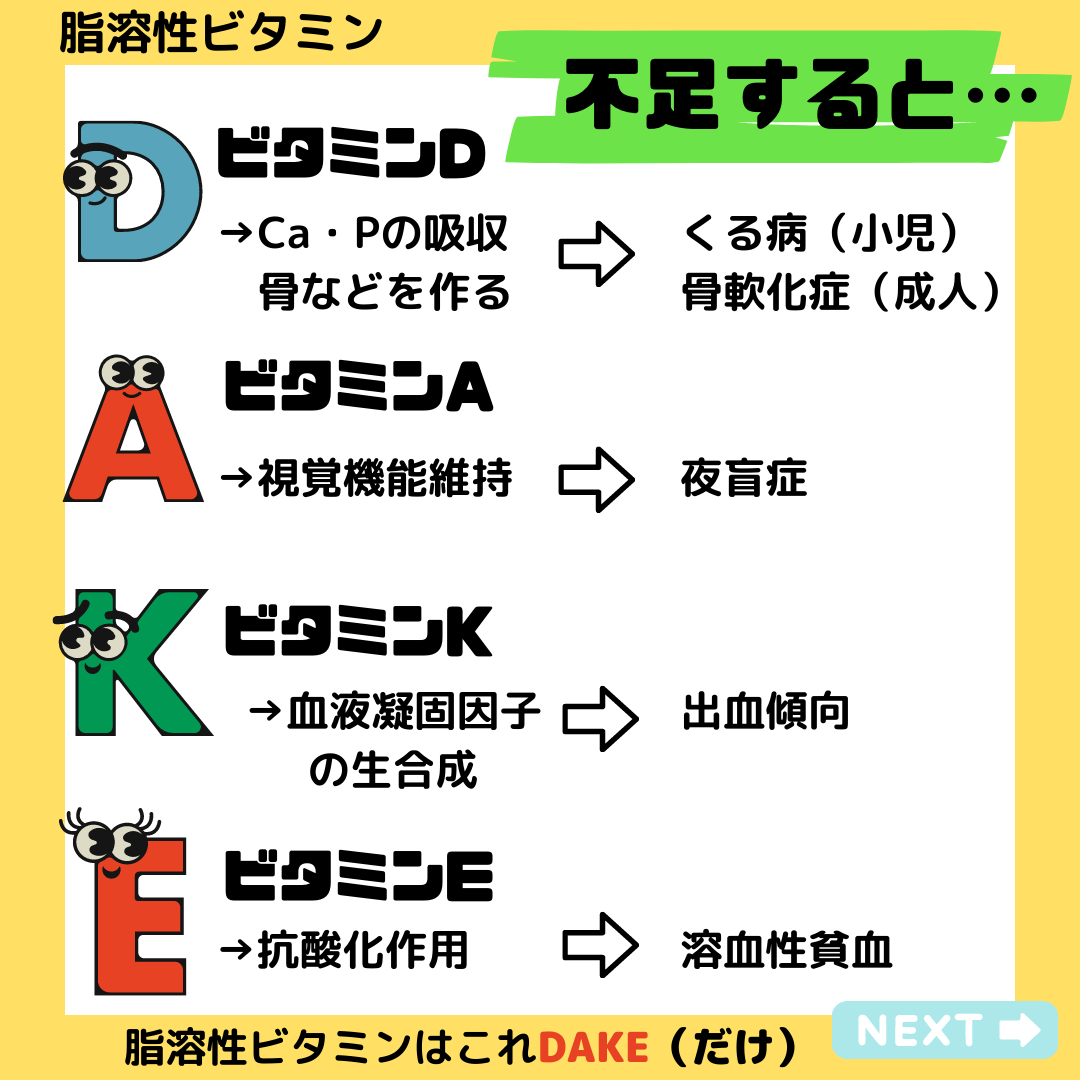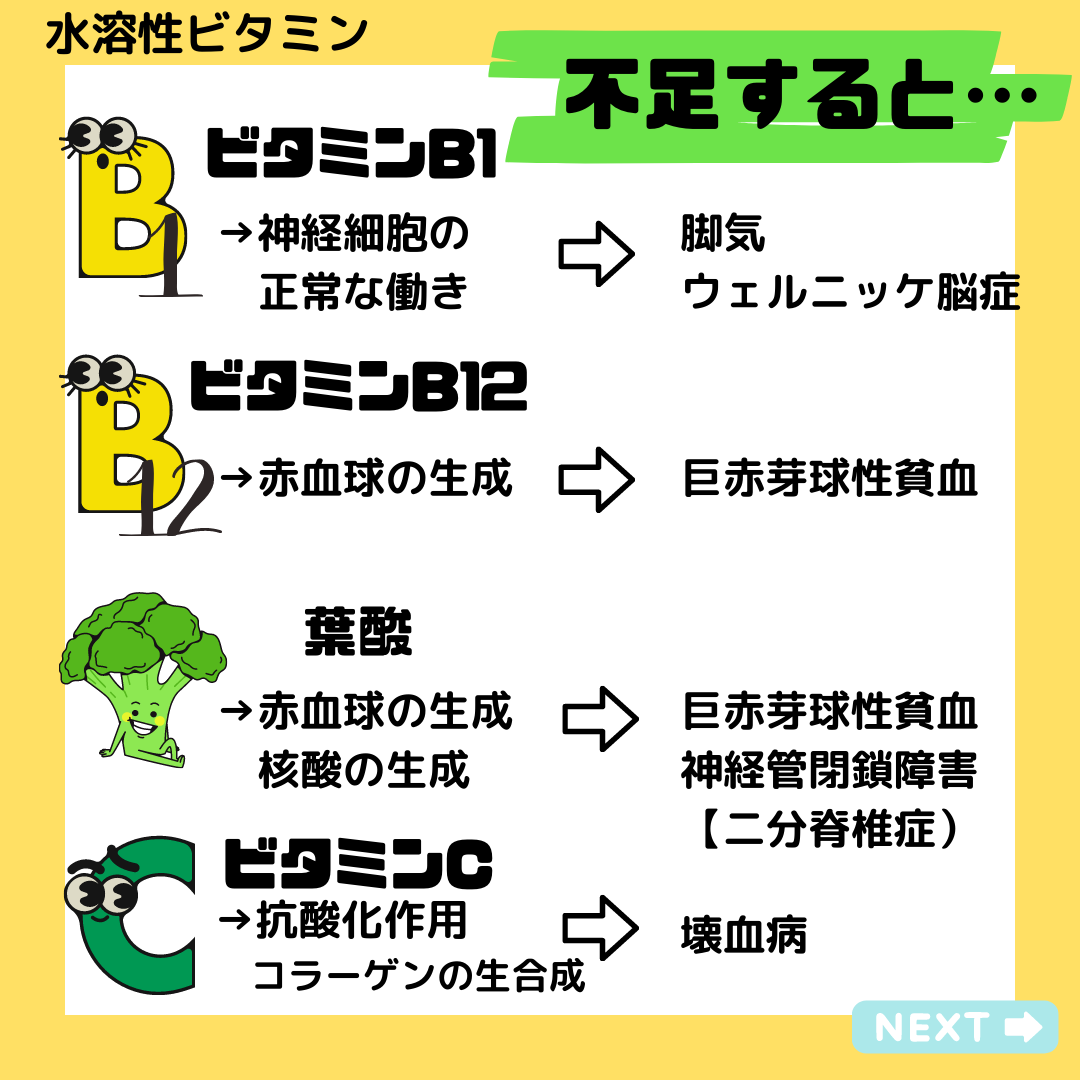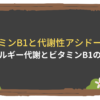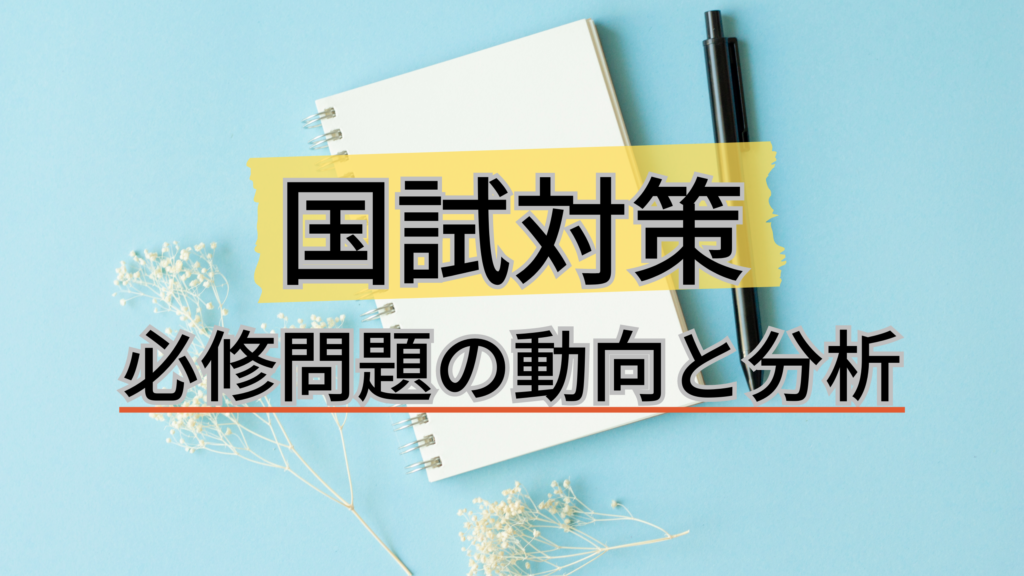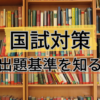こんにちは、講師のサキです。
今回は、看護師国家試験対策におすすめの問題集・参考書を紹介します。
第1位 レビューブック
看護師国家試験を受験するにあたり、必須アイテムと言っても過言はありません。
必ず購入することをおすすめします。
2025年版が3/8に発売されました↓↓
過去10年分の問題分析し、出題された問題を中心に構成されているため、教科書とは違い知りたいことを的確にポイントだけを知ることができます。
また、図表やイラストなど、受験生の理解を助けるための工夫も充実しています。
その上、2位、3位と続くQB(クエスチョンバンク)シリーズと連携しており、補足して勉強してほしいページなどが記載されている点も非常に優しいです。
使い慣れるために、低学年の頃から(実習で調べものをする時などから)使うことをおすすめしています。
受験年度のレビューブックがいるのか?という質問もよくされますが、1-2年程度であれば、古いレビューブックでも問題無いと回答しています。
統計データなどに若干の誤差はありますが、1年程度古いデータでも基本的には問題ありません。
そういう誤差を気にするよりも、いち早く使い慣れることをおすすめします。
第2位 QB一般(クエスチョンバンク)
国家試験の過去問は色々な業者から出版されていますが、上記のレビューブックとの併用を考慮すると、QBシリーズをおすすめします。
解説の丁寧さは他の業者も遜色無いですが、勉強のしやすさを考えるとQB一択です。
もちろん、他の過去問集が見やすい、使いやすいというものがあれば、他の過去問集でも問題ありませんので、とりあえず一般問題の過去問集を一冊は購入しておくことをおすすめします。
第3位 QB必修
QBシリーズの必修バージョンです。
一般問題集に加え、必修問題集も購入しておくことをおすすめします。
おすすめする理由は、QB一般と同様で、使い勝手が良いためです。
勉強を何から始めるのか?という問いに対しては、QB必修問題集から始めることをおすすめしています。
第4位 必修問題まんてんGET!
ここからは少し優先度が下がりますが、できれば購入しておきたい一冊です。
必修問題は8割以上の得点が必要な問題であり、全ての基礎となる分野になります。
QB必修問題集は基本的に過去問中心に構成されているため、若干難易度的に不安があります。
やや難しく、細かく分析した必修問題集を購入しておき、必修問題は満点をとれるように深く勉強することをおすすめします。
必修問題まんてんGETは適度に難しく、ポイントを絞って解説を構成しているので、短期間で必修の得点を上げることができると思います。
第5位 必修問題ファイナルチェック360問
こちらも必修の問題集です。
特徴は、オリジナルの予想必修問題360問を掲載しており、多くの問題を解き進めるというスタイルに仕上げているというところです。
解説はそこまで深めず、必要最低限に絞っているので、タイトルのとおりファイナルチェック的な問題集になります。
解説がややうすいという点で、一つ順位を下げました。
第6位 必修ラスパ
こちらも必修問題集です。第4・5・6位から一冊選ぶと良いかと思います。
必修ラスパも人気書籍で、丁寧な解説に加え、オリジナルの予想問題を400問程度掲載した、コンパクトサイズながらボリュームのある問題集です。
必修に止まらず、一般問題につながるように解説されている点も良いです。
ただ裏を返すと、必修問題集としてはボリュームが多く、状況によっては合わない場合もあるかと思い、順位を少し下げました。
第7位 でた問70% 高正答率過去問題集
こちらは、必修・一般・状況設定問題全てを網羅した問題集です。
特徴としては、過去5年間の国家試験から70%以上の問題だけを集めて構成しているという点です。
基本的に国家試験は正答率70%以上の問題を落とさずに正解できれば、合格に近づくと言われていますので、そこに絞っているようです。
また、難易度も易しめなので、取り掛かりやすいのも良い点です。
ただ、解説がうすいので、最初に取り掛かると丸覚えしかできないリスクもあります。
使い方を間違えずに活用できれば、重要な問題を集めてくれている問題集なので、使ってみることをおすすめします。
第8位 これで完璧!看護国試必修完全攻略集
さわ研究所から出版されている必修問題集です。
今まで出題された必修問題をほぼ網羅し、それに伴う必要な知識を全て丁寧に解説してくれています。
統計データなども、主要な順位・年度だけでなく、細かく掲載してくれています。
ただ、その分、必修問題だけにも関わらず、かなりのボリュームになるため、少し気が引けるのが残念なポイントです。
必修問題の辞書的な立ち位置になるかと思います。
第9位 これで突破!社会保障&関係法規
社会保障・法律・公衆衛生に特化した問題集です。
社会保障関連の問題が苦手な受験生が多いということから、作られた問題集かと思います。
かなり細かく出題されているので、難しい問題も多いですが、余裕があれば一度解いてみても良いかと思います。
法律など細かい部分まで理解できるようになります。
第10位 看護師国家試験 国試過去問題集
国家試験の必修から社会保障まで、分野毎に過去問の出題傾向を分析しています。
ボリュームは多いですが、自分の現在の理解度を分野毎に整理することができますので、ある程度学習が進み、余裕が出た段階で知識を確認していくのに良い参考書です。
まとめ
【強く購入を推奨】
第1位 レビューブック
第2位 QB一般
第3位 QB必修
【購入を推奨(1-2冊)】
第4位 必修満点GET!
第5位 必修ファイナルチェック360問
第6位 必修ラスパ
【自分に合えば購入しても良い】
第7位 でた問70%
第8位 これで完璧!看護国試必修完全攻略集
第9位 これで突破!社会保障&関係法規
第10位 看護師国家試験 国試過去問題集
今まで使ってきて使いやすいもの、受講生が活用していたもの、使いやすいと感じていたものを絞って、順位付けしました。
ただ、使いやすい問題集は個々で違いますので、参考にしつつ、自分に合った問題集を購入することをおすすめします。
この投稿をInstagramで見る