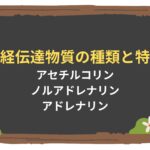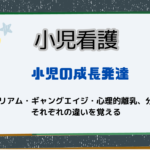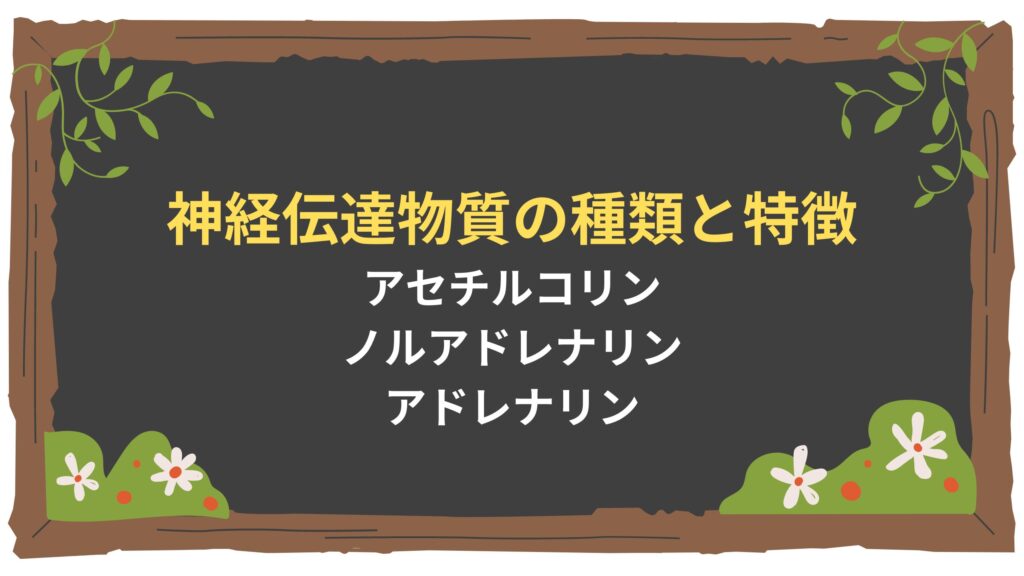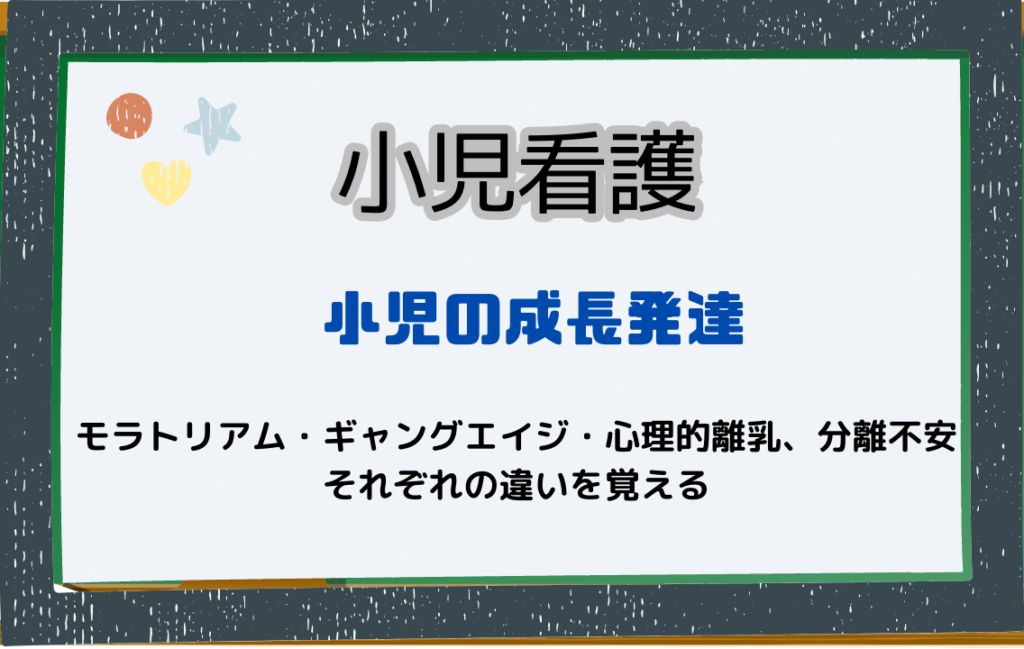こんにちは、講師のサキです。
今回は、神経伝達物質の種類と特徴 ~アセチルコリンとノルアドレナリン~です。
神経伝達物質は目に見えない上に、働きも様々で分かりにくい分野です。
神経伝達物質の種類は多いですが、国家試験に出題されるものは主要なものだけですので、全体を把握しつつ、主要なものの働きを覚えられるようにまとめました。
神経伝達物質の種類
国家試験で問われたことのある神経伝達物質は、以下の6種類です。
①アセチルコリン
②ノルアドレナリン(とアドレナリン)
③ドパミン
④セロトニン
⑤GABA
⑥グルタミン酸
頻出はアセチルコリンとノルアドレナリンなので、この2種は最後に解説します。
⑤GABAと⑥グルタミン酸:脳内でニューロンの働きに関与する
⑤GABAは最近テレビなどでも耳にする言葉かと思います。
働きは、中枢神経系(脳)で、ニューロンの興奮を抑制することです。
そのため、GABAをとることで、身体を落ち着かせることができるといわれています。
逆に、⑥グルタミン酸は、中枢神経系で、ニューロンを興奮させる作用があります。
④セロトニン:幸せホルモン
セロトニンは幸せホルモンと呼ばれているものです。
気分を落ち着かせる作用などがありますので、セロトニンが不足することでうつ症状になると言われています。
脳内でのセロトニンの再取り込みを阻害する薬が、抗うつ薬として使われています。(SSRI、SNRIなど)
③ドパミン:脳内報酬系の活性
ドパミンは、何かを達成したときに快く感じる要因となる神経伝達物質です。
中脳黒質から産生され、中枢神経系(脳内)作用します。
③〜⑥を問う問題は、あまり無いかと思いますが、予備知識として覚えておいてください。
①アセチルコリンと②ノルアドレナリンの違い
神経伝達物質の問題では、①アセチルコリンと②ノルアドレナリンが頻出です。
問題のポイントとなるのは以下の部分です
①アセチルコリンは副交感神経終末と運動神経終末での神経伝達物質であり、
②ノルアドレナリンは交感神経終末での神経伝達物質であるということです。
上記の特徴を言い換えると、
①アセチルコリンは、副交感神経の興奮によって収縮する筋肉と運動神経に支配される骨格筋を支配しているということです。
一方、②ノルアドレナリンは、交感神経の興奮によって収縮する筋肉を支配しています。
支配する筋肉についての問題が出題されるのは、この部分を理解できているかを問いています。以下のような問題です。
問. アセチルコリンで収縮するのはどれか。
- 1.心筋
- 2.排尿筋
- 3.腓腹筋
- 4.立毛筋
- 5.瞳孔散大筋
アセチルコリンで収縮するのは、副交感神経の興奮によって収縮する筋肉と運動神経に支配される骨格筋を選ばなければなりません。
まず一つ目は、3.腓腹筋です。
これは骨格筋ということで選びます。なんとなく理解しやすいかと思います。
次に問題となるのは、副交感神経の興奮で収縮する筋肉は何かを理解しておくことが必要です。
交感神経と副交感神経の違い
交感神経と副交感神経を簡単に説明すると、両者の違いは以下のようになります。
交感神経が興奮することで起こる身体の反応は、瞳孔散大、気管支拡張、脈拍増加、排尿筋の弛緩(畜尿)、立毛筋の収縮などです。
副交感神経が興奮することで起こる身体の反応は、瞳孔縮小、気管支収縮、脈拍低下、排尿筋の収縮(排尿)など交感神経と反対の反応が起こります。
つまり、アセチルコリンで収縮する筋肉=副交感神経の興奮で起こる身体の反応(収縮する筋肉)=排尿筋の収縮や瞳孔を収縮させる瞳孔括約筋になります。
選択肢の正解は、2.排尿筋となります。
(瞳孔散大させる瞳孔散大筋や立毛筋は、交感神経支配の筋肉となり、ノルアドレナリンの働きで収縮します。)
アセチルコリンとノルアドレナリンの働きをしっかりと理解して覚えることが大切です。
②ノルアドレナリンとアドレナリンの違い
最後に、ノルアドレナリンとアドレナリンの違いについてです。
どちらもカテコールアミンであり、作用など明確には区別して明記されていませんので、そこまで深く追い求める必要は無い部分かと思いますが、気になる方も多いので、簡単に説明します。
簡単に区分すると、アドレナリンはホルモン(兼神経伝達物質)、ノルアドレナリンはホルモン+神経伝達物質となり、アドレナリンの方が作用する範囲が狭いです。
基本的に、アドレナリンは副腎髄質ホルモンで血圧を上昇する作用などを持ちますが、血液脳関門を通過できないため、脳など中枢神経系では働きません。
ノルアドレナリンは、副腎髄質からも産生されますが、交感神経節でも産生される神経伝達物質でもあるので、中枢神経系でも働きます。(そのため、精神症状にも関わってきます。)
まとめると、産生場所の違いにより、作用範囲が少し異なるが、作用に大きな差は無いと考えて良いかと思います。
結局は、ストレスなどを感じると、自律神経が刺激され、アドレナリンやノルアドレナリンが放出されるため、血圧上昇、不安、恐怖などの身体症状が起こります。
まとめ
神経伝達物質は、6種類程度あるが、ポイントはアセチルコリンとノルアドレナリン。
①アセチルコリンは副交感神経終末と運動神経終末で活躍する神経伝達物質である。
②ノルアドレナリンは交感神経終末で活躍する神経伝達物質である。
アセチルコリンで収縮する筋肉、ノルアドレナリンで収縮する筋肉が分かるために・・
交感神経や副交感神経が興奮した時に起こる身体反応を覚えておくことが重要である。
アセチルコリンを止める薬が抗コリン薬・・と薬剤の話にもつながってきますので、難しいですが、しっかりと理解しましょう。