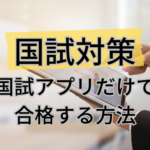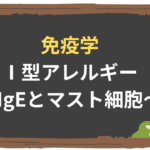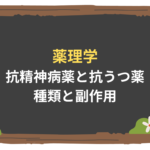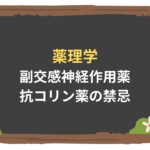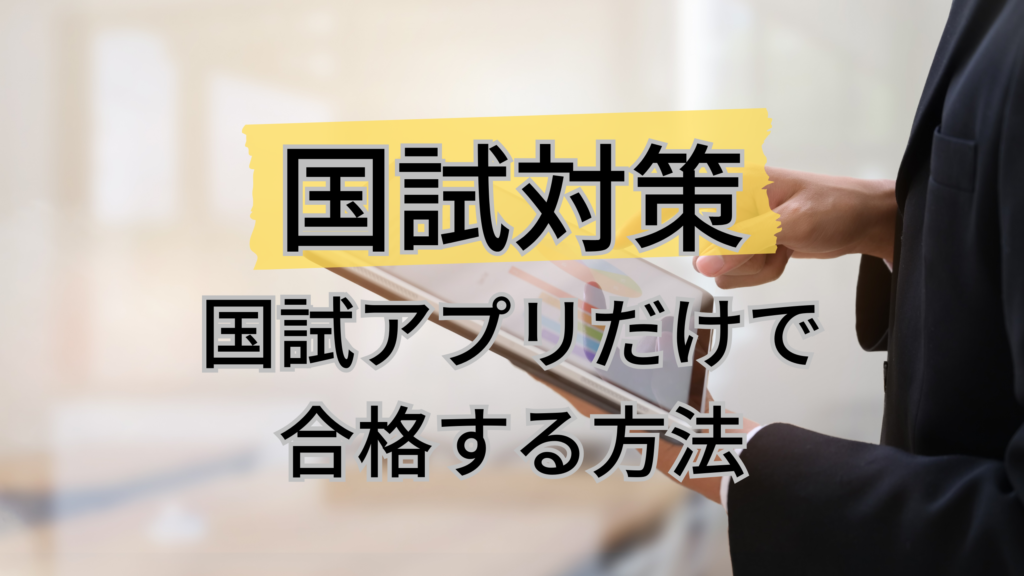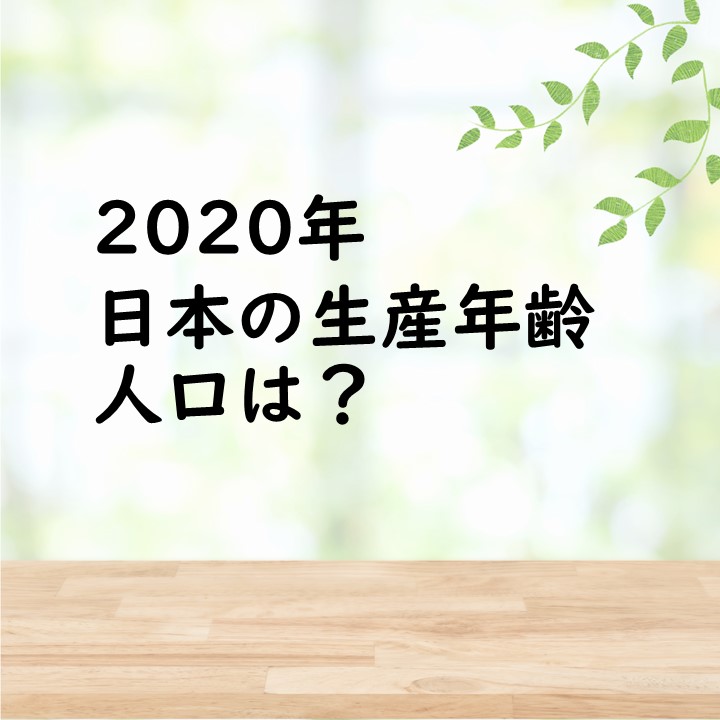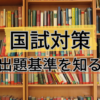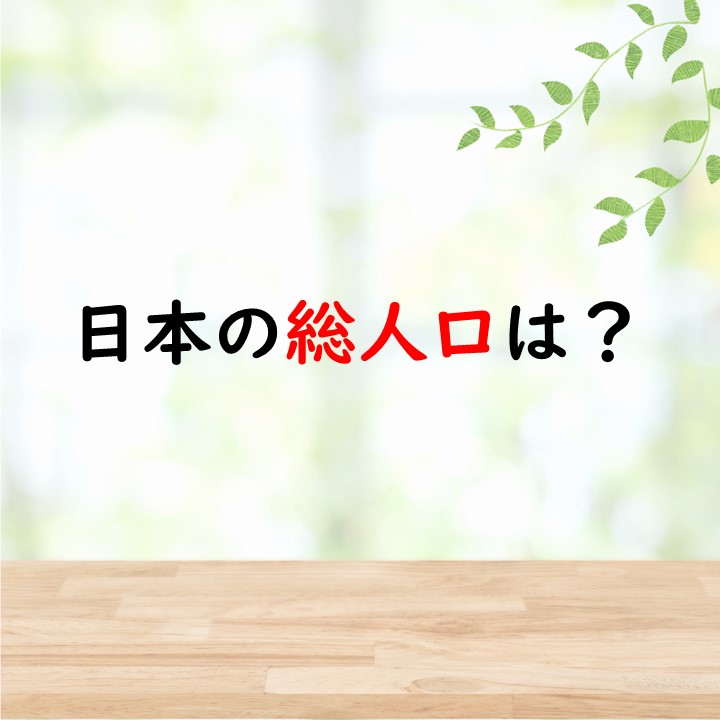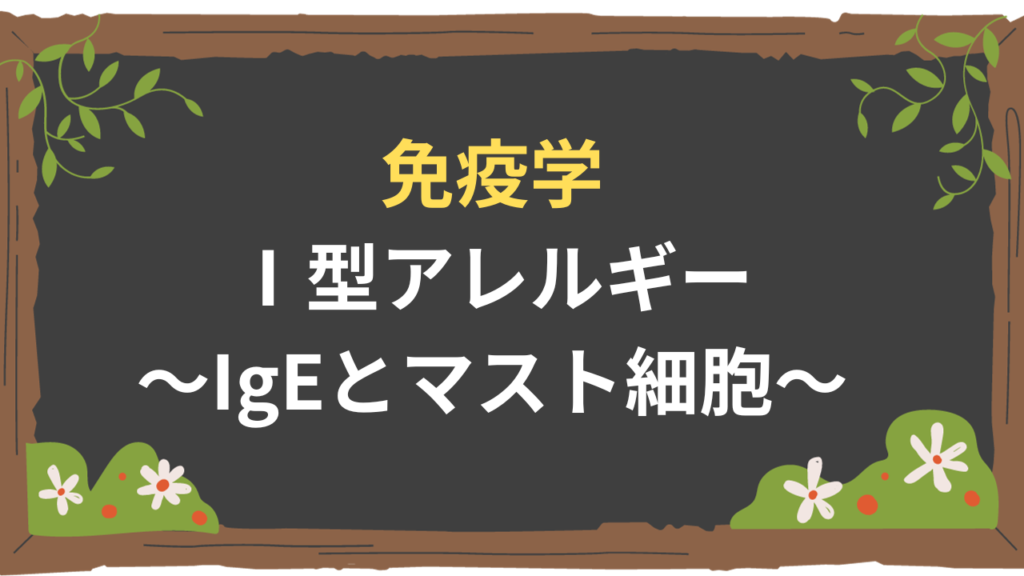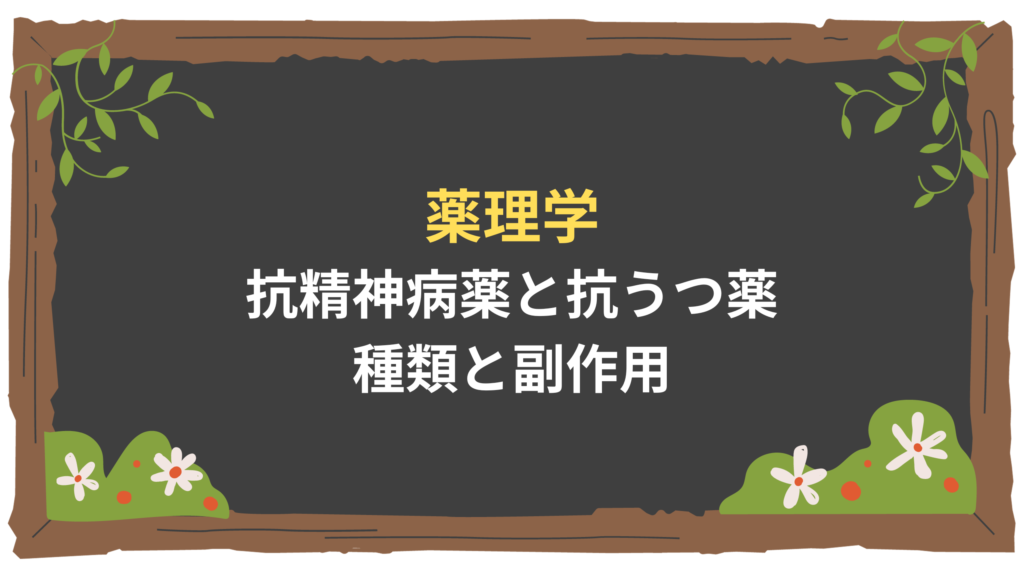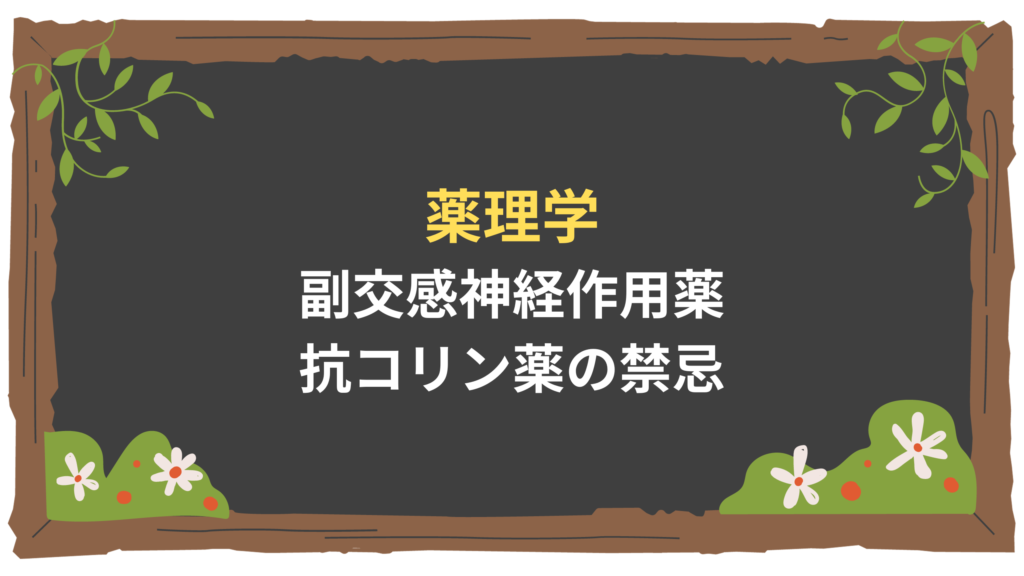こんにちは、講師のサキです。
今回は、看護師国家試験対策アプリだけで合格ができるのか、についてです。
国家試験対策といえば、QBなどの過去問集とレビューブックを購入し、繰り返し学習で知識を定着させていく、というのが一番オーソドックスな方法です。
しかし、学生の中には、過去問集やレビューブックを購入しないで、アプリだけで合格してしまう学生もいました。
結論、アプリだけで合格することは可能だということです。
※補足ですが、学校から配布されるプリントなどは解いていました。
※基本的には自分自身への前投資として、参考書等は購入することをおすすめします。
上記2点も踏まえ、アプリ学習のメリットと、アプリ学習のデメリットを克服する学習方法をお伝えします。
アプリの種類と特徴
看護師国家試験対策のアプリは何種類かありますが、よく学生が活用しているアプリは、看護rooかQB(クエスチョン・バンク)です。
その他にもありますが、そこまで大きな差は感じませんので、見やすさや使い馴染みの良さで選択すれば良いかと思います。
QBを購入している人であれば、連動しやすいので、QBアプリをおすすめします。
アプリの利点
①過去20年相当の全問題を解くことができる
②問題を年代別に解くこともできれば、分野毎に解くこともできる
③一問一答形式で解き進められ、正誤のポイントとなる解説もすぐに見ることができる
アプリも素晴らしい力を秘めていますので、ぜひ活用すべきだと思います。
アプリ学習のメリット
アプリ学習のメリットは大きく分けて3つあります。
①手軽さ
移動中や隙間時間を活用して、いつでもどこでも学習することができます。
分厚い過去問集やレビューブックを持ち運ぶだけでも辛い、机の上で開くのも辛い、という悩みが一気に無くなります。
学習に挑むハードルが低い分、はじめの一歩が出やすいです。
②効率的に問題が解ける
問題集やレビューブックなど、参考書というのは関連する必要事項はあれもこれも載せてしまう傾向にあり、文字の羅列に圧倒されてしまいます。
アプリの場合、問題を解くにあたり必要最低限の知識だけを載せており、あれこれ振り回されることがないので、解くスピートが上がります。
効率良く過去問を周回することができます。
③苦手分野をピックアップできる
問題集でも付箋を貼ったり、目印を付けたりすることで、苦手分野などをピックアップすることはできますが、紛れ込んでしまいがちです。
自分自身で理解している問題と理解していない問題を整理することが非常に大事です。
アプリの場合は、間違えた問題や自信の無い問題は、要復習問題として保存することができ、要復習問題だけを繰り返し解くこともできます。
間違えた問題の分野毎の分析もしてくれますので、自分の苦手分野も分かります。
(得点率の低い分野は解剖生理・病態生理など、そもそも国家試験で得点率が低い分野に集まることが多いので、参考程度で良いかと思います。)
アプリ学習のデメリット
アプリ学習のメリットの裏返しがデメリットになります。
①手軽く始められる分、手軽に止められる
スマホアプリになるため、誘惑に負けることが多々あります。
電話などの通知、様々なSNSを活用できるスマホの中で、勉強アプリを使い続けられるかが鍵となります。
紙の参考書の場合は、スマホを手元に置かずに学習するなどの工夫ができるため、集中力を保って学習することも可能ですが、アプリは難しいです。
相当の精神力が必要になります。
②効率的な解説の分、解説が物足りない
関連事項をあれもこれも載せていない分、関連して覚えてほしいことが抜け落ちてしまうことが多々あります。
関連して覚えたり、知識を深めたりすることができないという点から考えると、アプリ学習はやや非効率な方法になってしまうかもしれません。
系統的に学習するためには、関連した知識をつなぎ合わせていくことが重要になります。
一問一答形式のアプリの最大の弱点とも言えます。
③苦手分野のピックアップ
裏返しで記述してきたので、苦手分野のピックアップ欄も作成しましたが、アプリ学習の苦手分野のピックアップ能力は素晴らしいので、特にデメリットありません。
ただ、苦手分野をピックアップしたところで、苦手分野を丸暗記するしかアプリ学習の場合、方法はありません(解説が不十分なところが多いため)。
効果的なアプリ学習方法
上記のメリット・デメリットを踏まえた上で、おすすめのアプリ学習方法を紹介します。
①アプリ学習のためのスマホやタブレットなどを用意する(おすすめはipad)
学習専用端末を作ってしまう戦略です。
普段使いしているスマホで無ければ、不要な通知がありません。
また、他の誘惑のあるアプリを入れなければ、集中力も保ちやすいかと思います。
使っていないスマホなどを活用しても良いかと思いますが、学習用の端末としておすすめはipadです。
②解説だけでは関連事項が不十分な場合は調べる
アプリの解説だけでは根拠などが不十分で、覚えられない、知識が定着ができないと感じた場合は、深く調べることが重要です。
一番手軽な方法は、分からない問題をスクリーンショットして保存し、その解説をネットや教科書で調べ、調べた内容もスクリーンショットなどで一緒に保存しておくことです。
ipadをおすすめする理由としては、問題のスクリーンショットと解説のスクリーンショットをgoodnotesのアプリなどにまとめていくことができるため、手軽にノートが作れるという点でかなり便利です。
③苦手問題は10周解く
アプリ最大の利点は、数多くの問題を手軽に進めることができるということです。
苦手問題に限らず、何周も過去問を解き続けていきましょう。
周回を重ねることで、何回しても覚えられない問題や、何度も出てくる問題が分かってきます。
そういった問題をピックアップし、②に挙げたような方法で深く覚えていくようにする、というような段取りで行うのをおすすめします。
最初から頻出問題や重要な問題、関連事項を調べた方が良い問題などが分かる訳ではありません。
④必修問題は100周するつもりで周回する
必修問題は8割(40/50点)に満たなかった時点で不合格になる、超重要項目の問題です。
絞るまでもなく必修問題はすべて重要項目になりますので、100周するつもりで解き進め、分からない問題はノートにまとめるなどしましょう。
必修問題は第93回から設定され、ようやく20年になるので、問題数は850問程度であり、基礎的な項目も多いので、周回するのもそこまで難しくはありません。
参考までに、、アプリ学習で合格した学生は、国家試験の1ヶ月前からは、必修850問を毎日解くようにしており、その結果必修は49/50点とれていました。
もちろん②のようなまとめ学習も取り入れていましたが、周回による暗記の効果もかなり出ていたと思います。
アプリ学習の筆者の意見
最後に、筆者の意見は、アプリだけで合格を目指すのは非効率であり、あまりおすすめはしない、ということです。
しかし、手軽に多くの問題を周回でき、苦手問題を分析してくれる、というアプリのメリットはしっかり活用すべきだと考えています。
アプリ学習のデメリットを補うためには、やはり紙の参考書などをベースとして活用し、参考書で学習した内容を忘れないためにアプリで周回するというサポート的な活用をおすすめします。
アプリ学習で合格を目指すための方法のまとめ
①学習用の端末を用意する。できればipadを活用し、goodnotesなどのノートアプリと連動させる。
②アプリに収録されている20年分の問題(5000問相当)を周回する。
③何度も出題される問題、理解しづらい問題が分かってくるので、その問題はノートにまとめたり、調べたりすることで不足を補う。
④必修問題は100周するつもりで周回し、満点を目指す。
アプリ学習に限らず、国家試験の勉強はいかに周回を重ね、大事な問題や苦手な問題を理解し、勉強に活かしていけるかが重要になってきます。
紙ベースではやる気が出ないが、アプリならやる気が出るという人もいるのも事実ですので、自分に合った学習方法を見つけてあげることも大事にしてください。